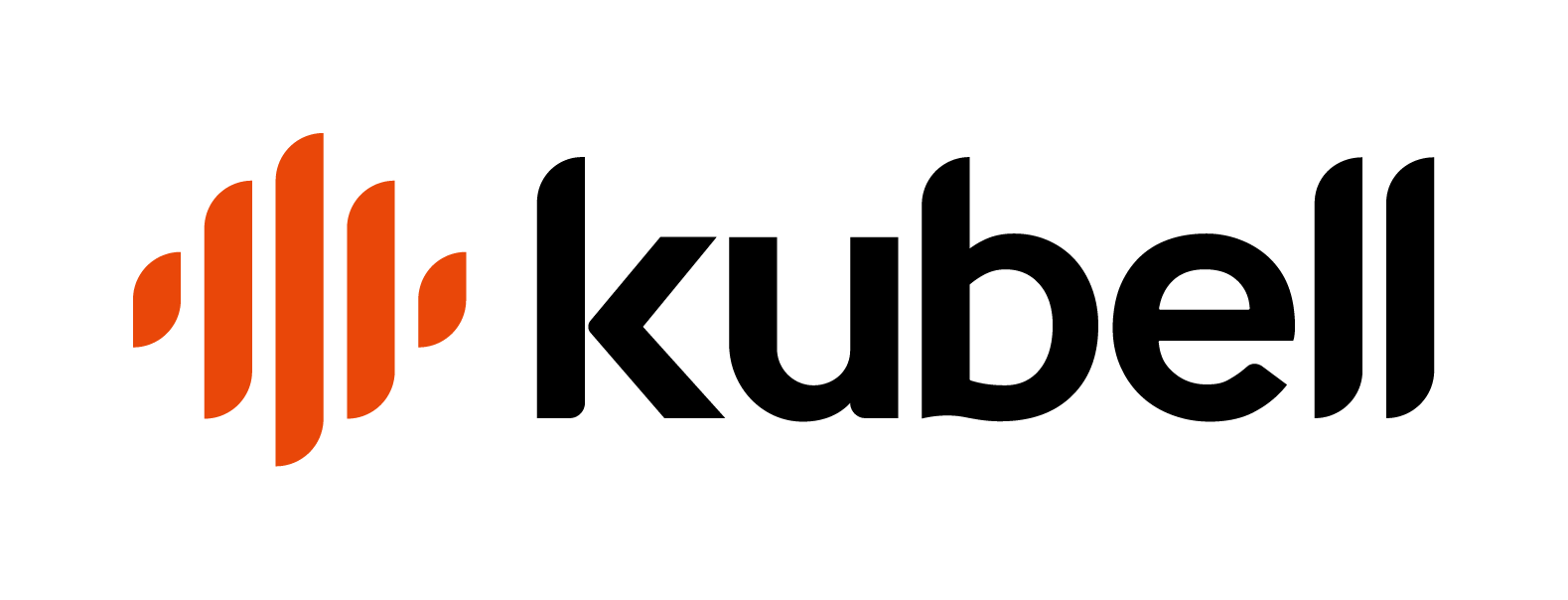楽じゃない。でも面白い──1人目QAというキャリアの選び方
プロフィール
稲垣 直子
コミュニケーションプラットフォームディビジョン
プロダクトユニット QAグループ
エンジニアリングマネージャー
前職のCRMクラウドサービス事業を手掛けるマーケティング会社でQA(品質保証)チームを立ち上げ、自らもQAエンジニアとしてプロダクトのテスト計画立案から実施、評価、報告等の業務に従事。2023年11月に、kubellでは1人目となるQAエンジニアとして入社し、幅広く品質改善活動に取り組んだのち、2024年11月よりQAグループのエンジニアリングマネージャーを務める。
田中 佑樹
執行役員CTO
SES企業にてWeb系システムの開発に従事したのち、2013年にChatwork株式会社(現 株式会社kubell)に入社。UI刷新プロジェクトのWebフロントエンド開発や外部向けREST API開発、メッセージ検索サーバー刷新など数多くのプロジェクトを担当。その後エンジニアリングマネージャとして、プロダクト領域の幅広い領域のマネジメントを経験したのち、2023年3月にプロダクト本部長、2023年10月に執行役員、2025年7月に執行役員CTOに就任。
品質に向き合うという選択──“テストチーム”を越えて見えた役割
──では最初に、稲垣さんのこれまでのキャリアについて伺ってもよろしいでしょうか?
稲垣: これまで20年程、品質に関わる仕事をしてきました。組み込み系や大規模基幹システムやSaaS等様々なプロダクトに携わってきました。今は株式会社kubellで「Chatwork」プロダクトをメインに担当する部門のQAグループでエンジニアリングマネージャーをしています。去年立ち上がったばかりの組織で、私はその1人目として入社しました。
──QAとしてのキャリアがかなり長いんですね!
稲垣:そうですね、ウォータフォール開発からアジャイル開発まで様々なプロダクトに携わってきました。特に前職のSaaS企業の経験が長く、8年間QA業務を担当していました。当初は開発が完了したものをテストする、いわゆる”テストチーム”に配属されました。しかし、そのタイミングでは対応が遅く、もっと早い段階から関わっていたら良かったのにと思うことも多かったんです。
その頃、外部の勉強会にも足を運ぶようになり、社外の取り組みに触れたことで視野が一気に広がりました。社外の事例を聞く中で、「開発中のプロセスに踏み込むQAの役割」を知りました。当時は全てが新鮮で、実際に社内にも一つずつ取り入れていきました。QAが関わる幅を広げていった結果、チーム名も”テストチーム”から”QAチーム”に変わり、リーダーとして数名をマネジメントしていました。
──実際にチームとしての役割が変わっていったんですね、具体的にどのような取り組みをされていたのでしょうか?
稲垣:本来QAチームは”テストすること”が目的ではなく”品質を担保すること”が目的だと考えています。なので、早い段階から開発プロセスに関わることにしました。出来上がったものをテストしてフィードバックするよりも、仕様を決める段階から「こういう場合はどんな振る舞いになりますか?」という質問をするだけで、「そのパターン考えていなかった!」というような議論が生まれるんです。
開発者は担当領域を、本当に深いところまで理解しています。しかし、大きなプロダクトの場合は特に、担当外の領域やプロダクト全体を考慮することは難しいと思っています。そこに違う視点を持ったQAエンジニアが入ることで新たな議論が生まれ結果的に品質向上につながったと思っています。

“誰もいない”からこそ惹かれた──1人目QAという挑戦
──なるほど、ありがとうございます。かなりやりがいを持って取り組まれていたのかなと思うんですが、転職を考え始めたきっかけを教えてください。
稲垣:前職では多くの取り組みを通して、QAとしての幅を広げられたという実感はありました。ただその達成感と同時に、今後は自分のスキルを伸ばすだけではなく、”QA組織を拡大し会社全体で品質を上げていきたい”と思うようになりました。とはいえ、個人の希望だけではなかなか難しい部分もあったので、この目標を実現できる環境を求めて少しずつ社外にも目を向け始めました。
──実際転職活動を始めるにあたって、不安な部分などありましたか?
稲垣:前職には8年間在籍していたため、転職は自分にとって身近ではなかったので、そもそもどうしたら良いのかわからなかったです。当時は、ただただ“怖いな”という気持ちが強かったのを覚えています。
それこそ前職の転職時は、面接のためにスーツで直接企業に伺うような時代でしたので、その印象が強くて(笑)。前回の転職では、情報収集や日程の調整をほぼ一人で進める必要があり、正直大変だった記憶が強く残っていました。なので外の環境に目を向けはじめたものの、実際に行動には移せずにいました。
そんな時に、Findyさんが主催していたQAイベントに参加したことがきっかけでユーザーサクセス面談を受けました。元々、会社に不満がありすぐに辞めたいという状況ではなかったのですが、面談時に市場のことや他社の情報を教えていただき、徐々に転職活動をしてみても良いかもと思っていきました。kubellもその面談内で紹介いただきました。
変わりたい。でもまだ怖い──動き出した“半歩”の転職活動
──実際に様々な企業を知る中でkubell社について話を聞いた最初の印象はいかがでしたか?
稲垣: 「Chatwork」自体は前職で使っていたので知っていました。最初は、本当にQAエンジニアがいないということが信じられなかったです(笑)。あとは、1人目ということで正直ハードルが高いなと思ったのですが、一方で、自分のやりたいことにチャレンジできるかもしれないというワクワクもありました。
──実際にCTOの田中さんは稲垣さんとお話しされた印象を覚えていらっしゃいますか?
田中: kubellとしても、当時は品質保証やテストをエンジニア組織だけで担うことに限界を感じていて、QAの専門組織を立ち上げる決断をしました。そこで、マネジメント経験があり組織立ち上げができる方を探していて、その中ですごくぴったりな方だと思ったのを覚えています。
── 実際に選考の場では、お互いにどんな印象を持たれましたか?
稲垣: 面接は正直緊張していたんですが、田中さんとお話ししたときに「ちゃんと話を聞いてくれてるな」と感じたんです。自分の経験や考えをしっかり受け止めてくれて、意見を押しつける感じも全くなく対等に話してくださったのが印象的でした。「この人たちとならやっていけそう」と、安心感を持てたのを覚えています。
特に今回は“1人目のQA”という立場で入るからこそ「どんな人たちと一緒にやっていくのか」はすごく重要だと考えていました。QAの役割はどうしても開発者と対立関係になりやすい側面があります。一方的に指摘するのではなく、互いに協力し合える関係が大事だと思っています。だからこそ、選考で田中さんと会話したときの、ちゃんと対等に向き合ってくれると感じたことが決め手になりました。
田中: 私もすごく印象に残ってます。稲垣さんはご自身の取り組みや考え方をきちんと伝えてくれて、こちらの質問にも丁寧に向き合ってくださって。「この人となら一緒に立ち上げていける」という感触がありました。

──実際に1人目の採用となると企業としても重要なポジションだったのかなと思うのですが、稲垣さんとの面接で重視していたポイントはありますか?
田中: QAが「門番」にならないことです。エンジニアチームもQAチームも良いものを作り上げたいという本質的な目標は同じです。しかし往々にして、役割的に最後の門番になりチェックをする部門となってしまう場合があります。最終チェックだけを担うのではなく、現場の課題を理解してどうQAプロセスを作っていくかを一緒に考えてくれる人。その点で、稲垣さんと話した時に「まず現状を把握して、シフトレフト的に入っていく」という考え方は、我々の方向性とも一致していたのを覚えています。
──最後に、稲垣さんがkubellに入社を決めた理由を伺ってもいいですか?
稲垣:他の企業さんでは、既に優秀なQAエンジニアがいて組織の仕組みも整っている印象がありました。もちろん学ぶことは多いと思いますが、自分がそれをなぞっていくイメージよりもゼロから戦略を描いて形にしていく方が、きっと楽しいだろうな、と思えたんです。
正直、転職活動を始めたと家族に話した時は表立って反対こそされなかったものの、「大丈夫..?」という反応でした。でも最後kubellにしようと思うと話した時は、企業として知っていたということもあり「いいんじゃない?」と応援してくれたことも大きかったです。
──ご家族の応援も素敵ですね!実際に入社後、QAの立ち上げということで具体的にはどのような動きから始めたんですか?
稲垣: まずは開発チーム全体へのヒアリングから始めました。各チームがどんな課題を抱えているのかを丁寧に聞き、「Chatwork」にとって理想的なQAのあり方を考えました。入社直後は「本当に自分でできるのかな」と不安に思うこともありました。でも、同時に「これが自分の力を試すチャンスなんだ」と気持ちを奮い立たせて、できることから少しずつ取り組み始めました。
正解がない状況で動く怖さはありましたが、だからこそ、丁寧に耳を傾けて信頼関係を築くことが何より大事だと感じていました。情報共有のために社内LTで「こういうことを目指します」と発信したり、QAとしてのスタンスを理解してもらう工夫をしていました。
── 組織の中でのコミュニケーションはかなり配慮されたんですね。
稲垣:やはり、立ち上げ当初はかなり気を遣いました。ちょっとした違和感や戸惑いが、組織全体の信頼に関わる可能性があるので「できるだけ摩擦を起こさないように」ということはすごく意識していました。
でも、ただ迎合するわけではありません。「これは違う」と否定するのではなく「こういうやり方もありますよ」と提案することで、少しずつ現場と共に考えるスタンスを取れるようになってきたと思います。そうした丁寧なやりとりの積み重ねが、やっと少しずつ形になってきたと感じています。声をかけてもらいやすい雰囲気を作ったり段階的な進め方を意識しました。
──よく候補者の方から、組織でQAの役割が理解されにくいという話を耳にすることもありますが、実際にQAチームを立ち上げいく段階で、現場の"品質"に対する意識は根付いていたのでしょうか?
田中:そうですね、ビジネスチャットという性質上、品質がプロダクト価値にかなり直結する部分があります。実際チャットツールなのでユーザーが接してる時間がとても長いこともあり、品質に対する意識は高くて。実際にQAチームができる前からCICDを自分たちで導入して自動化するのはもちろんですが、その重要性に関しては感じているエンジニアが多かったです。
また、会社としてのカルチャーも大きかったかなと思います。QAは他の開発と違って「何かを新しく生み出す」わけではなく、あくまで“品質を高める”ことが主な役割です。だからこそ組織のトップがその重要性を理解していないと、組織として積極的に体制を広げていく対象にはなりにくいこともあると思います。その点、kubellでは現在のCEOが元々CTO出身ということもあり、開発への理解や品質への関心が元々根付いていると思います。
背伸びし続ける日々──“できないかも”の先にあった確かな成長
── 稲垣さん自身、入社前と比べてどんな成長を感じていますか?
稲垣: 転職直前は、ある程度の経験も重ねていたので、正直なところ「100%出し切らなくても業務が回る」という状態だったんです。でも、kubellに入社してからは「常に背伸びしないと達成できない」ような挑戦ばかりです。自分の未熟さや課題に日々直面しています。
最初はそのギャップに戸惑うことも多く「あれ、自分ってこんなにできなかったかな?」と焦ったり、周囲のスピードについていけているか不安になったり、ちゃんと役に立っているのかなと考える場面も多かったです。しかし、一つ一つ振り返るようにしていて、最近はうまくできないことも含めて前向きに受け止められるようになった気がします。
また、以前は「自分がどうしたいか」を考えていましたが、今は「チームメンバーのキャリア」や、「組織の成長」を常に考えるようになりました。そういう意味では、自分の軸が『個人』から『チーム』へとシフトしたことが一番の成長だと感じています。

──最後に、今後kubellで取り組みたいことを教えてください。
稲垣:チームメンバーが入社するまでは自分がプレイヤーとして動いてきましたが、今後はチーム全員でしっかり成果を出していきたいと思っています。「QAチームができて本当に良かった」と言ってもらえるような組織に成長させていきたいです。
田中: 稲垣さんに作っていただいたQAチームの戦略を実現してもらいたいとは引き続き思っています。あとは、去年の7月に社名が変わってkubellという会社になって、グループ企業として今後成長していく中で、グループ全体の品質のあり方についても全社最適な戦略についても今後推進していただきたいと思っています。