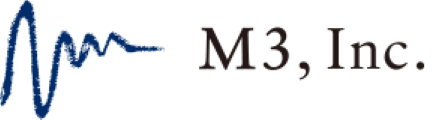エムスリー4代目CTO就任。AI時代に布石を打った“神の一手”の真相
2025年4月エムスリー株式会社(以下、エムスリー)は、同社でAI・機械学習チームリーダーを務めていた大垣慶介さんを新CTOに、前CTOの山崎聡さんがCPO(Chief Product Officer)に就任したことを発表しました。
2000年創業のエムスリーは、医師向け情報プラットフォーム「m3.com」や、クラウド型電子カルテ「エムスリーデジカル」など、医療業界の革新的なプロダクトを生み出してきたテックリーディングカンパニーです。そんな同社では、時代の先を行くプロダクト開発を行うための重要な意思決定を、“神の一手”と呼んでいるそう。
生成AI黎明期とされる今、AIへの注力を象徴する今回の人事転換は、必ずや今後の行方を示す “神の一手”になるでしょう。テクノロジー分野の中でも早期に発足した同社のAI・機械学習チームは、これまでに何に取り組み、どのような成果を上げたのか。時代を先取る両名はこの先の時代をどう見ているのか、そして今後目指すエムスリーのエンジニアリングについて、大垣さん、山崎さんに聞きました。
プロフィール
大垣慶介さん
エムスリー株式会社 ゼネラルマネージャー / CTO、エムスリーAI株式会社 取締役CTO
東京大学情報理工学系研究科卒。Web企業でのMLエンジニア/リサーチャーを経て、2019年同社へ入社。AI・機械学習チーム、m3.com開発チームを含む複数チームの担当ゼネラルマネージャーを兼任しながら、2025年4月より現職。研究の専門は機械学習・コンピュータビジョン(被引用数450+)
山崎聡さん
エムスリー株式会社 取締役CPO / CAIO、エムスリーテクノロジーズ株式会社 代表取締役
大学院博士課程中退後、ベンチャー企業、フリーランスを経て、2006年メビックスに入社。2009年エムスリーグループ入り以降、主にプロダクトマネジメントを担当した後、VPoE、CDO、CTO兼VPoPを歴任し、2025年4月より現職。同年5月よりCAIO(Chief AI Officer)を兼任
CTO・CPO・VPoEの3本柱で、AI民主化を早期に実現する

—— MLエンジニアであり、AI・機械学習チームのリーダーである大垣さんがCTOに就任されたことは、時代を象徴するセンセーショナルなニュースでした。交代の理由や狙いについて教えてください。
山崎:大垣のCTO就任は、AIを活用したさらなるプロダクト強化が狙いです。振り返ればエムスリーでは歴代のCTO交代が、会社のギアチェンジのきっかけになっていました。まずウェブサービス台頭期に今も続く基幹ビジネスである「m3.com」を安定稼働させた初代CTO Brian Hooper。大規模SaaSへのシフトに伴い発生した、超難易度の開発を成し遂げた2代目CTO 矢崎聖也。エンジニア組織のプロダクト組織化が求められた時代にそれを推進した3代目CTOである私、山崎。
そして今回、AI・機械学習プロダクトを率いてきた大垣にCTOをバトンタッチすると同時に、私はCPOに就任しました。同じくAI・機械学習を専門とするVPoE河合俊典を合わせた3トップ体制で、AI活用に振り切っていきます。
一言に“AI活用”と言いますが、開発環境にAIを取り入れ効率化する“AI活用”と、プロダクトにAIを組み込み利便性を向上させる“AI活用”、2つの意味が含まれています。この目的が異なる2つのAI活用をよりスピード感持って実現するためには、テクノロジー・プロダクト・組織づくりという3方面からのアプローチが最適だと考え、この体制に変更しました。
—— これまでもテクノロジーの変遷を先読みした人事をしてきたんですね。一気にAI活用の波が来た、この時代の流れをどのように捉えていますか?
大垣:世間では“AI活用の時代”と言われていますが、より正確には“AI民主化の時代”だと感じています。というのも、プロダクトのAI実装はすでに当たり前になっており、エムスリーでもほとんどのプロダクトにAIが組み込まれています。
例えばNetflixのようなレコメンド中心の体験は、典型的なAI活用の事例ですが、こうした仕組みではユーザーにAIを意識させない形で提供されてきました。なぜなら多くのユーザーはAIを能動的に使うことを、まだ望んでいなかったからです。
しかし今は、そんなユーザー心理にも変化が見え始めています。AIを意識的に活用したい人が増え、裏側にあったAIが表側に出てくるという意味で、一般ユーザーがAIを当たり前に使う時代、つまりAIが民主化された時代に入った、と言えるのではないでしょうか。この時代の変革に合わせ、今後すべてのソフトウェアには、ユーザーが触れられる形でAIが実装されていくでしょう。エムスリーのプロダクトでも、そんな状態をいち早くつくることが、私たちの役目です。
プロダクトのAI実装ですでに大きな利益を上げている

—— エムスリーでもすでに成功例があるとのことですが、具体的なAI活用例を教えてください。
大垣:最もわかりやすい例を挙げると、「m3.com」のトップページはいまや9割以上がAIでレコメンドされており、今日読むべき記事やニュースが集約されています。またクラウド型電子カルテ「エムスリーデジカル」では、医師が日頃行う処方から学習したAIが病名や処方薬の予測をしてくれるので、カルテ作成を効率化できています。このように、この10年は、AIでユーザーの体験を改善することが重視された時代で、当社でもAIを使ったユーザビリティ向上で年々事業を伸ばしてきました。
山崎:実際にAI・機械学習チームが創出した利益額を見ると、目を見張るものがあります。15名ほどの小規模組織でありながら、年間数億円規模の利益を上げる複数のプロダクトをコンスタントに生み出し続けていますし、今後も順調に増加する見通しです。AIを活用したプロダクトの開発が盛んになっているとはいえ、これほどの事業インパクトは他に類を見ない功績です。
—— エムスリーのAI・機械学習チームが、これほどの成果を出せたのはなぜですか?
大垣:まず最もミクロな理由は、AI・機械学習チームの責任範囲が広く、当事者意識を強く持ってAI実用化を推進してきたからです。例えばあるプロダクトのトップページにおすすめ記事の表示を提案する際、そのプロダクトの開発チームへ事例を助言したりAIツールを配布するのではなく、「この枠を任せてください」と働きかけ委任してもらう体制を取りました。
つまりAI・機械学習チームでは、企画・開発・運用に一貫してコミットしていて、AIのアルゴリズムはもちろん、それを呼び出すAPI、Kubernetesでのインフラ、さらにはWebサービスのフロントエンドやスマホアプリ(PWA)の開発まで、すべて行っています。
横断組織が各プロダクトへ改善策を提案するだけでは、結果を相手に委ねるような一種の無責任さがあると考えています。やはりこうして自分たちがプロダクトの開発にコミットして進めることこそが、最速の成果につながると実感できました。
山崎:さらに言えば、AI・機械学習チームが活躍できる組織体制をつくれたからとも言えます。組織という点では、弊社の風土を象徴するような逸話があります。
実は、AI・機械学習チームの初仕事は、社長肝入りのアルゴリズムを改善した、というものだったんです。
エムスリーでは、創業期からユーザーへのメールマガジンでのコミュニケーションに非常に力を入れているのですが、どのくらい注力していたかというと、創業社長の谷村が定例会議に出席して、自ら現場と議論しながらルールベースのアルゴリズムの検討に関わるくらいの熱量だったんです。
ところが、2017年にAI・機械学習チームを立ち上げた直後、その定例会議に出席した機械学習エンジニアが「機械学習ならより良いレコメンドができますよ」と言い出しまして、実際2週間後に持ってきたモデルが既存のアルゴリズムを部分的に上回ってしまったんですね。
平たくいうと、社長が手塩にかけたものに軽く喧嘩を売った訳なんですが(笑)、もともとA/Bテストの文化が根づいていたこともあり、谷村も含めて満場一致で「じゃあ、こっちでいいじゃん」となり、真にユーザーが欲しているものを速やかに実現するためには、是々非々でデータやテクノロジーを活用していくことが近道だという共通見解ができたと聞いています。
エムスリーでは誰が言ったかより、何を言ったかを重視する風土が根付いていますし、ユーザーが真に欲しているものを実現するために、データやテクノロジーがその近道になると全員が理解して業務に取り組んでいるんです。
徹底的な現場主義が最速で最高。さあ「主人公になろう」

—— 今回の人事転換で新たなステージにギアチェンジされますが、引き継がれるエムスリーらしさはなんでしょう?
大垣:CTO就任を機に、私は「主人公になろう」というスローガンを掲げました。これは当社のエンジニアリング文化である、徹底的な現場主義を再解釈したものです。
私がCTOに着任した後も、技術選定は引き続き各チームリーダーに任せています。いわば全エンジニアが主役で、我々ゼネラルマネージャーは彼らを支援する存在です。使いたい技術スタックがあれば、導入のためのPoCや承認の義務はなく、プロダクトに最適なものを各自の裁量で選択してもらっています。
また開発組織で言えば、1プロダクトあたりエンジニア3〜5名という少人数組織でもきちんと成果が出ているのは、現場主義たる由縁だと思います。全員が仕事の範囲を狭めずプロダクトに向き合い、本当につくるべき機能にフォーカスしたり、より効率的な設計を提案したりすることが自然にできているのです。こうした環境が、最速で最高のプロダクト開発につながっていると実感しています。
山崎:そうですね。ユーザーが喉から手が出るほどほしいものを考え、それがどうやったら実現ができるのか、技術的な観点で最も解像度が高いのは現場のエンジニアです。そのため個人の裁量が大きい環境にしているので、言うなれば、全員が主人公になるしかないんです。逆に言えば、指示待ちの人には辛い環境だと思います。当社はこれまで多くのCTOやVPoEを輩出してきましたが、それも現場主義やプロダクト志向で鍛えられたからかもしれませんね。
出遅れ感を抱くのはまだ早い!生成AI活用はこれから

—— 現場主義に加え、今後はAI活用の先端事例も身に付くとなれば、エムスリーは若手エンジニアが実力をつけていく上で、最高の環境になりそうですね。どのようなエンジニアに入社してほしいですか?
大垣:これまで通り、ギークでスマートなエンジニアというキーワードは変わりません。ただAI活用を視野に入れると、技術面に限らず幅広い分野での“オタク”を想像しています。
繰り返しになりますが、今後はすべてのソフトウェアにAIが組み込まれ、全エンジニアがAIを活用することになります。そうなった時、自分なりの“オタク領域”があるエンジニアにこそ、プロダクトを飛躍的に成長させるアイディアを生み出せると思うんです。
例えば動画のエンコーディングにとても詳しいエンジニアなら、動画のキーフレームの圧縮にAIを活用すると効率化できるのではと気づけますが、そもそもキーフレームがなにかを知らない人には絶対に思いつけないですよね? 私自身、AI・機械学習チームリーダーとして、AIでやるべきことはかなりわかっているつもりなのですが、他のエキスパートの視点によって気付かされるAI活用ポイントが今でも毎日のようにあります。
つまりこれからは、技術面に限らず、医療・製薬業界のドメイン知識やユーザー特性なども含めて、その人なりのオタクな視点を持つ人が活躍できる時代になると思います。今の時点での生成AIに関する豊富な知識は、必ずしも必要ではありません。
山崎:そうですね。生成AIの波が来た今の状況って、インターネットが普及した1992〜93年頃にそっくりなんですよね。今ではインターネットを使わないエンジニアがいないように、全エンジニアが生成AIを活用し効率化する時代になります。今AI活用が身近でない人はちょっと遅れ始めていますが、まだ大丈夫です。
AIをつくる方向ではなく、活用して効率化をしていけばいいんです。これはエンジニアの三大美徳、怠惰・短気・傲慢にぴったり当てはまります。技術的な好奇心やチャレンジ精神を持って、新しい時代を一緒につくっていける方に、ぜひ入社していただきたいと思います。興味を持ってくださったら、求人票から「いいかも」をお待ちしております。