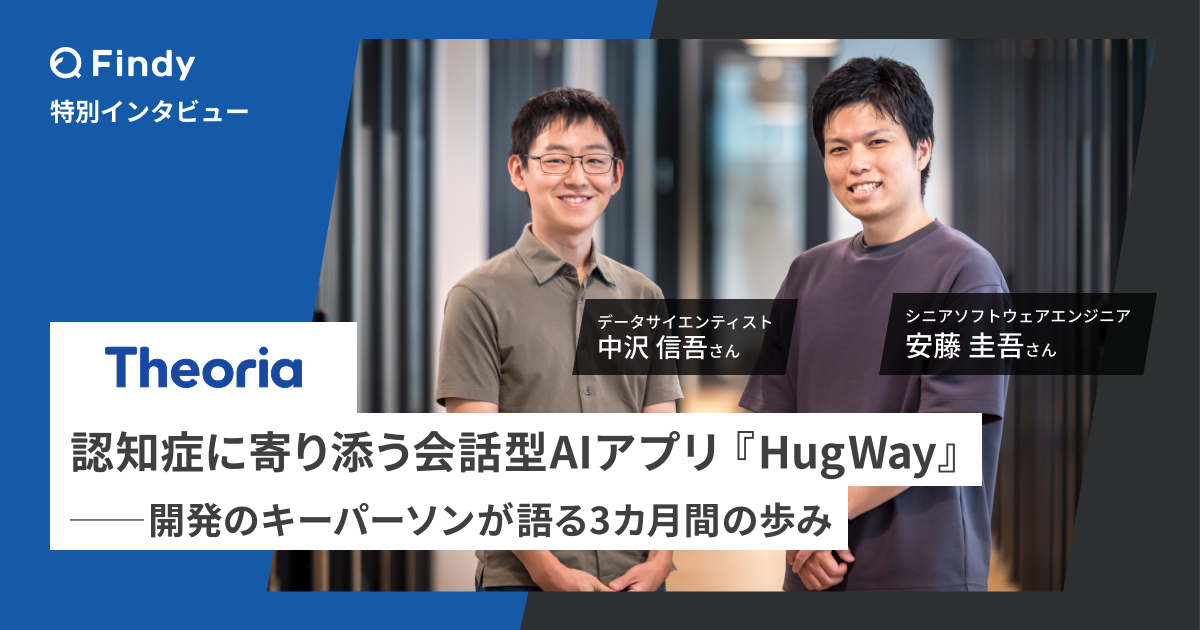
“認知症”という社会課題にAI技術で立ち向かう テオリア・テクノロジーズで挑戦するエンジニアたち
技術で世の中を変えたい――そのように考えたことのある方は少なくないでしょう。適切なアプローチと環境があれば、エンジニアの技術は確実に社会を変える力になります。
大手製薬会社エーザイの子会社であるテオリア・テクノロジーズは、認知症にテクノロジーという新しい答えで挑むスタートアップ。同社が開発したのが、人生のターニングポイントを迎え、孤立しがちな60代に寄り添う会話型AIアプリ「HugWay」です。
HugWayの開発現場では、出力を完全に制御できない生成AIや薬機法という厳格な規制などの課題に直面したといいます。そのような困難に立ち向かい、わずか3カ月という短期間でのリリースを成功させた立役者のお2人にインタビューを実施しました。
制約のある環境で成果を出すには?社会課題に技術で向き合う方法と、そこで得られる技術者としての成長を探ります。
プロフィール
安藤 圭吾さん
シニアソフトウェアエンジニア
執筆した技術本をカンファレンスの即売会で売るというところからキャリアをスタート。Web技術とゲームエンジンの拡張を主軸に、フルスタックエンジニアとして開発者に向けてより良い環境を提供していくことに従事。2025年2月よりテオリア・テクノロジーズに入社。現在はバックエンド・インフラ担当としてそなえる領域を担当。
中沢 信吾さん
データサイエンティスト
総合研究大学院大学および国立遺伝学研究所において新生仔脳の発達をテーマとした研究に従事し、博士号を取得。その後、スイス・ジュネーブ大学にてバイオインフォマティクスを活用した基礎研究に携わる。帰国後はデータサイエンティストおよびシニアデータサイエンティストとして、民間企業への統計・機械学習技術の導入支援を多数手がける。2025年1月にテオリア・テクノロジーズに入社。プロダクト開発を進めると同時に急速に発展する生成AI技術を社内にいち早く導入し、全社への普及を担当。
「病院に来ない人」に技術の力でアプローチ

――まずは、テオリア・テクノロジーズが認知症という社会課題にテクノロジーで取り組む背景について教えてください
中沢:当社の親会社であるエーザイ株式会社は、認知症領域を注力領域として長年にわたって認知症治療薬の開発に取り組んできました。しかし世の中には、体質的に副作用が強く現れるため薬物治療を受けられないなど、薬だけでは救えない患者さんも存在します。
こうした薬物治療の対象外となる方々が認知症になったとしても希望を持てるような世界をつくることが、私たちがテクノロジーに取り組む大きなきっかけになっています。
安藤:一方で薬物治療ができたとしても、認知症の初期症状に気づかず医療機関を受診しないまま症状が進行する――。そんな患者さんもたくさんいます。
例えばエーザイで2023年に国内で承認・発売されたアルツハイマー病治療薬は、MCI(軽度認知障害)や認知症の初期段階で投与を始めることになりますが、薬の提供に加え患者さんに寄り添いフォローすることが望まれます。
そこで私たちは、認知症の早期発見・早期介入を実現するために、日常的に使用するスマートフォンアプリなどのデジタルツールを通じて、医療機関受診のきっかけを提供することが有効だと考えました。
デジタルツールには、人々の日常生活に自然に溶け込むという特性があります。この特性を活かして、認知症という課題にアプローチすることを目的に開発したのが、会話型AIアプリ「HugWay」です。
60代の孤独に寄り添う会話型AI「HugWay」
――「HugWay」とはどのようなサービスなのでしょうか?

安藤:「HugWay」はAIを活用した会話チャットアプリケーションです。
利用者との会話を通じて、歩数データや睡眠データなど、個人の特性や生活パターンを示すデータをもとに会話を構築しています。孤独感による気分の落ち込みを防ぎ、前向きな生活を支援することを目的としています。
中沢:「HugWay」が主要ユーザー層に設定しているのが、60代の方々。この年代は、子どもの独立による生活環境の変化や定年退職による社会的役割の変化など、人生における重要な転換期を迎える時期です。まさに社会との接点が急激に減少するタイミングでもあり、認知機能の低下や生きがいの喪失を経験する方が多く見られます。社会とのつながりを維持し、第二の人生への移行を支援する存在の必要性があるのです。
――従来のヘルスケアアプリとの違いはどこにありますか?
中沢:一般的なチャットアプリケーションにみられるQ&A形式のやり取りと違って、HugWayは「雑談相手のような存在」であることを重視しています。
質問に対する回答を提供するのではなく、自然な会話を通じてユーザーの生きがい発見や新しい挑戦への動機付け、過去の興味関心の再発見などのきっかけを提供することを目指しています。
社会とのつながりを維持・構築するためのツールとして活用していただくことが基本的なコンセプトです。
――リリース後、ユーザーからの反響はいかがでしたか?
安藤:特に印象的だったのは、HugWayのAIキャラクター「ハグまる」の寄り添う力が高く評価されていることです。あるユーザーからは、他のAIを活用したサービスでは得られない満足感を感じているというフィードバックをいただきました。
そのユーザーは、ChatGPTやGeminiなど他のLLMサービスも使用経験があるものの、比較検討した結果としてHugWayを選択してくださっています。私たちが調整したAIのレスポンスが、ユーザーのニーズに適切に対応できているという手応えを感じています。
また、ユーザーの多くが「ハグちゃん」など独自の愛称で呼んでくださっており、単なるツールではなくキャラクターとして親しまれていることが確認できています。
―― その他に反響などありましたか?
安藤:自治体の方から認知症のそなえとして住民の方にも使っていただきたいといった声やハグまるを通じて自治体の情報を発信していけると良いといった声もいただいています。
HugWayとしても自治体のイベント情報や住民に届けたいさまざまな情報を、アプリを通じて提供する仕組みの構築を考えています。
従来の情報提供とは異なり、HugWayが相談相手として機能することで、地域住民と自治体をつなぐ役割を果たせる可能性は大きいと思っています。単なる情報発信ツールではなく、住民の本音やイベント参加への不安を聞き取り、それを自治体側にフィードバックできる双方向のコミュニケーションを目指しています。
――従来の自治体からの情報提供にはどのような課題があったのでしょうか?

安藤:従来の情報提供方法はチラシや掲示板への掲示など、多くが一方通行なものでした。自治体側から情報を発信するだけで、住民からのフィードバックを得る仕組みがほとんどなかったのです。
この場合、参加しない人がなぜ来ないのかの理由がわかりません。また、運良くイベントに参加した人からも「ちょっと忙しくて」といった簡単なフィードバックしか得られず、本当の理由を把握できていませんでした。
――参加に際し、どのようなハードルがあるのかまで把握できていなかったのですね
安藤:はい。例えばちぎり絵のワークショップに対しては、ちぎり絵をやったことがないから参加したくないと感じる方がいます。また、どういう人が参加しているのかわからないことへの不安もあります。
こうした生の声は従来の方法では届きにくいのが現状です。参加への心理的な障壁を理解せずに、同じような情報発信を続けても効果的ではありません。
――HugWayではこの課題をどのように解決するのでしょうか?
安藤:HugWayがこれらの本音をキャッチアップして、自治体にフィードバックしたり、当社のデータベースに蓄積。その蓄積されたデータの傾向を分析することで、ユーザーに最適なアクションを提案できるようになります。
例えば、「前回参加した初心者の方も、最初は不安でしたが、講師のていねいな指導で素敵な作品をつくることができて、とても楽しんでいました」といった具体的な情報を提供することで、参加への不安を解消できます。
また、収集した情報は、エーザイとテオリア・テクノロジーズが目指している“健常者から認知症の方までの幅広いケア”に活用できると考えています。
若い頃から蓄積された行動パターンや嗜好のデータは、将来認知症になった際の支援にも役立つ可能性があります。単なる情報提供ツールではなく、長期的な健康管理と社会参加を支援するプラットフォームとして機能させるのが目標です。
初の自社開発プロダクト!少数精鋭チームの奮闘記

――ここからは開発の裏話をお伺いしてまいります。まず、HugWayの開発体制について教えてください
安藤:開発体制としては、プロダクトマネージャー1名、デザイナー2名、バックエンド・インフラ担当の私1名、Flutterエンジニアがリリースまでは1〜2名体制で進めました。また、AIエンジニアとして中沢さんが参加し、その他にインターンの方やマーケティング担当1名も含まれていました。
専任で開発に集中できたのは、バックエンド・インフラ担当の私とFlutterエンジニア1名で、その他のメンバーは兼務での参加という形でした。
HugWayはテオリア初の自社開発サービスであり、既存のシステム基盤が一切ない状態からの開発がスタートしました。
――リリースまでは少数精鋭での開発体制だったのですね
安藤:本来であれば、各分野のスペシャリストが集結し、それぞれの専門性を活かした開発体制を構築するのが理想でした。しかし、リリースまでの時間的な制約もあって実現が困難でした。
そのため、私がフルスタックエンジニアとしての経験を活かし、フロントエンド、バックエンド、インフラ、運用監視システムまで幅広い領域を担当することになったのです。
中沢:私はこれまでのキャリアで開発経験がほとんどなく、テオリア入社時点でサーバー技術に関する知識を持っていませんでした。
AIエンジニアとしてHugWayの開発を任される中で、わからないことをひたすらAIに聞き、安藤さんにも頼りながら技術習得を進めました。アプリ開発未経験からのスタートでしたが、なんとかリリースまでの期間で必要なスキルを身につけることができました。
安藤:AI機能の開発は中沢さんにほぼお任せしてしまったので、本当に中沢さんの献身的な取り組みがあったからリリースできたというのが実情です。限られた時間とリソースの中で、それぞれが持てる力を最大限発揮した結果だと思います。
ヘルスケア領域×生成AI開発の特殊性
――生成AIを活用した開発ならではの難しさはありましたか?
中沢:生成AIは出力を100%コントロールできないという根本的な問題があります。通常のシステム開発と異なり、同じ入力でも毎回異なる応答が生成される可能性があるため、品質管理がとても難しい。加えて、HugWayがテオリア初の自社開発プロダクトであったため、そもそも社内ルールを一から策定する必要がありました。生成AIを活用したヘルスケアサービスに関するガイドラインや運用方針を、開発と並行して整備していく状況でした。
――ヘルスケア領域ならではの制約もあったのでは?
中沢:はい。薬機法の規制が大きな制約となります。診断行為の禁止や治療行為に関する言及の制限など、他の領域とは異なる厳しさが存在します。
AIが誤って医療的な診断や薬剤に関する不適切な情報を提供することがないよう、プロンプト設計や出力監視の仕組みを慎重に構築する必要がありました。これは技術的な課題であると同時に、法務・コンプライアンス面での課題でもあります。
不確実性に備える技術選定とアーキテクチャ
――LLM基盤はAmazon Bedrockを採用されていると伺いました
安藤:はい。ただし、現在はさまざまなLLMを使ってコストを下げつつ品質の良い会話ができるよう、複数のモデルを評価できる体制を整えようとしています。Bedrockのみに限定するわけではなく、最適な選択肢を見つけていく方針です。
中沢:Bedrock上で利用可能な複数のモデルを比較検討した結果、Claudeが最も寄り添い感を表現できるという判断に至りました。開発段階では定量的な評価よりも、実際にさまざまなモデルやプロンプトを試行しながら、最も適切な応答を生成できるという感覚的な評価をより重視していました。さまざまなモデルや異なるプロンプトを試行しながら、最も適切と感じられるものを選択しています。
もちろん、言ってはいけないことを言わないか、暴力的な内容や性的な内容を含まないか、薬機法に抵触する診断行為や治療行為に関する発言がないかといった定常的な監視も並行して実施しています。
――技術基盤の設計で工夫された点はありますか?
安藤:プロダクトの方向性が変わっても対応できるよう、柔軟な設計を採用しました。具体的には、API Gatewayを活用した拡張可能なアーキテクチャを構築し、後から機能追加や仕様変更に対応できる体制を整えています。
――なぜそのような柔軟な設計が必要だったのでしょうか?
安藤:開発チーム内では、HugWayのコンセプトについて頻繁に議論が発生しました。会話アプリなのか、ヘルスケアアプリなのか、その位置づけでメンバー間の意見が右往左往することが多く、方向性がブレやすい状況でした。
中沢:AIの返答も最初はもっと運動重視で、ひたすら歩数の話をしてくるような時期もありました。「本当にこれで行く」という方向性を決めるまでが、すごく苦労したところでしたね。
会話品質を向上させるための工夫
――AIの会話品質向上のためにどのような工夫をされたのでしょうか?
安藤:会話の品質は、一般的なユニットテストやインテグレーションテストでは測定できません。そこでユーザーペルソナを作成し、そのペルソナとAIに会話をさせるという独自手法を試しました。
50代から60代、70代の人で、どこに住んでいて、1日のルーチンがどのような感じで、家族構成はどうなのかといった詳細な人物設定を作成します。その人格を形成する情報を与えて、AIエージェントからの会話を受け取ったときにどう返答するかのテキストを生成させました。
――どのくらいの規模でテストを実施されたのでしょうか?
安藤:リリースまでの期間は約20人のペルソナを作成し、実際の本番環境で毎日会話をさせて反応を確認していました。
この手法はシステムが正常に動作するかの確認に重点を置いていたため、リリース後は運用方針を変更しています。現在はペルソナの会話内容をまとめ上げて、レポートを作成しやすくする仕組みに発展させています。
――このペルソナテスト手法をさらに発展させる構想はありますか?
安藤:現在のペルソナ設定では、テキスト量の上限により1日の行動パターンまで詳細に組み込むことが困難です。
今後はClaude Codeのような大容量のコンテキストを処理できるLLMや、NCPやToolsといった機能を活用して、日付に応じた具体的なスケジュール情報をペルソナに付与する予定です。例えば、「今日が月曜日なら朝は散歩、昼は買い物、夕方は孫の迎え」といった、その人らしい日常のパターンを動的に組み込むことができます。
これにより、健常の状態から徐々に認知症になっていく過程のシミュレーションや、認知機能の可視化も可能になると考えています。
AIエージェントを手軽に。全社で進む意識改革

――中沢さんは社内AIエージェント基盤「Theoria LLM Lab」を立ち上げられたと伺いました。立ち上げの背景について教えてください
中沢:私が会社から与えられたミッションの一つは、生成AIを社内で普通に活用している会社になるための基盤をつくることでした。
この基盤には2つの目的があります。1つ目は、社員向けに便利なAIツールを提供することです。メール作成などの実務を通じて、AIエージェントは特定のタスクに活用できる手軽なツールなんだということを理解してもらいたかったんです。
2つ目は、データサイエンティストとしての技術実験の場として活用することです。毎日のように新しい技術が登場するため、それを試す場所が欲しかったんです。最先端の技術を入れてみて、何か作って、会社の中で使ってもらえる環境があれば、そこから将来的にプロダクトの種につながるものが生まれてくる可能性もあります。
――そもそも、なぜ他社のAIサービスを利用せずに自前で基盤を構築されたのでしょうか?
中沢:自前で構築すれば自由度が高く、簡単に作って壊せるからです。他社サービスはお金を払ってしっかりしたものが利用できますが、まずその使用方法を学習する必要がありますし、使わない機能もありがちです。
Labでは必要最小限の機能を最速で提供することを目的としています。HugWayもそうでしたが、アプリのコンセプト検証もLabがあることで「動くもの」を手早く社内共有できて高速に進められています。また、AIコーディングを自由に試す場所としても有用です。本当に壊れても構わない実験環境として活用しています。
――中沢さんが書かれたnoteには「新しい言語モデルが発表されたら翌日にはLLM Labに搭載され、社内の全員が触れるようになっている」とありました。驚異的なスピードでの機能追加を実現できる理由は何でしょうか?
中沢:これはAIがコーディングをサポートしてくれるようになったことが大きな要因です。今はまだ自分でコードを書いたほうが速いことも多いのですが、Labのコードはあえて100%AIに書かせて、どの程度時間がかかるかを実験しています。簡単なタスクであれば完全にAIに任せて良いラインが見えてきたので、そうした作業は夜中に依頼しておけば朝には完成しているという状況です。
――社内での具体的な活用事例について教えてください
中沢:例えばインタビュー記事の作成では、インタビューの音声文字起こしを自動で行い、その結果から記事の雛形を作成し、さらに校閲まで行うといった一連の流れを自動化しています。
また、最近追加された画像生成機能を使って、HugWayのAIキャラクター「ハグまる」を地域の特色に合わせてカスタマイズした「ご当地ハグまる」を作成し、営業担当者が商談の際に提案資料に載せるといった活用法が生まれました。

こうした予想外の使い方を見ると、技術を提供する側だけでは発想できない活用法があることを実感しますね。
技術で認知症という社会課題に挑戦しませんか?
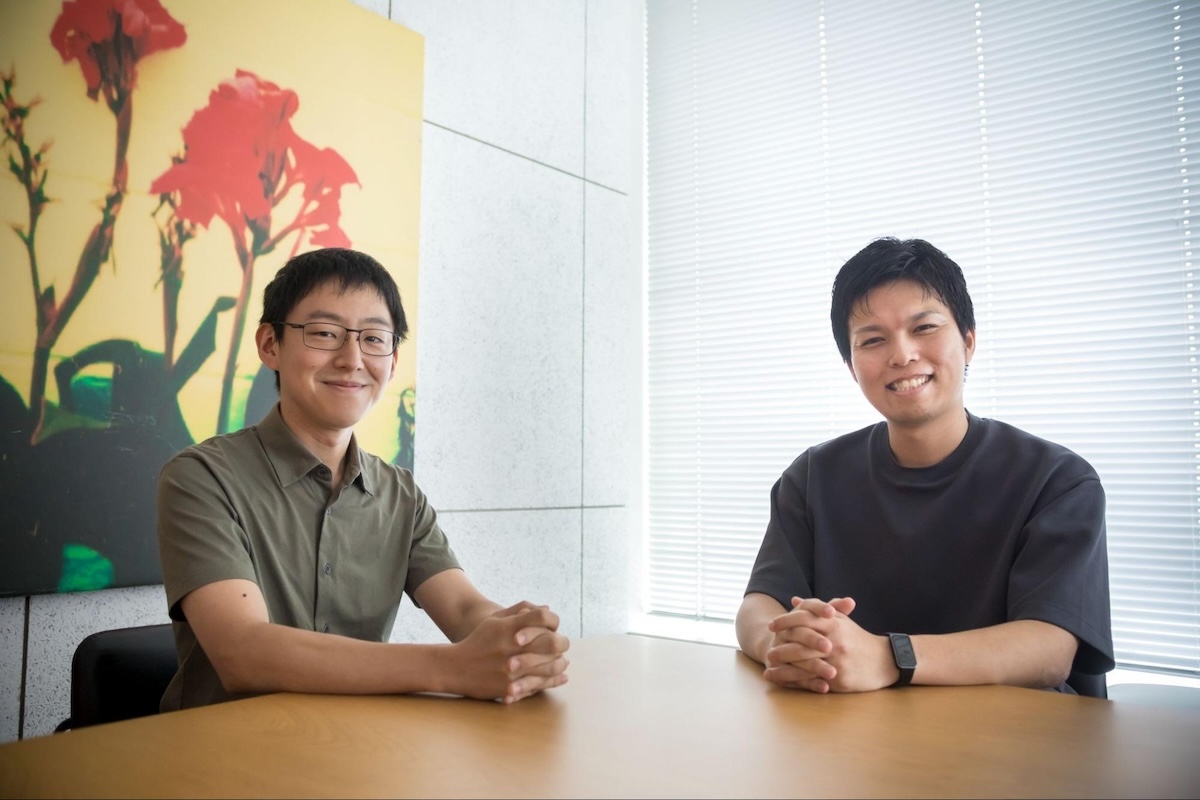
――現在、開発組織はどのように運営されていますか?
中沢:当社の開発組織は、自律分散型組織として現場メンバーが主体的に判断し行動するカルチャーを重視しています。
組織の規模はどんどん拡大しており、今後このスタイルを維持するかを検討するタイミングがやってくるかもしれません。しかし、現場主導で自発的に行動する組織文化は継続していく方針で考えています。
――テオリア・テクノロジーズが目指している開発組織の姿について教えてください
安藤:認知症は誰でもなる可能性のある病気であるため、対象となるユーザーの背景が多様です。ひとつの特定の解決策を提示しても、10人に1人程度にしかマッチしないという状況が発生します。
明確な答えがない課題に対して、どのように設計し、開発し、ユーザーに届けていくかを考える必要があります。とにかく届けないとそのユーザーにとっての答えが見つからないので、ひたすら届けて届けまくる。そのような環境づくりが欠かせません。
そのためには、各プロダクトチームが自律的に機能を開発し、スピーディーにユーザーに提供できる技術基盤が重要です。そこで現在、HugWayで構築したシステムを活用したプラットフォーム事業を展開し、各チームが効率的に開発を進められる環境を整備しています。
中沢:私たちがサービスを提供する対象は、社会的に脆弱な立場にある方々です。認知症の当事者や、介護により時間的・精神的な負担を抱えている方も多くいらっしゃいます。
こうした方々が利用するプロダクトを開発する企業として、生成AIネイティブな企業として、AIを活用したサービスの安全性と有用性を実証し、社会に示していく責任があります。AIに対する不安を払拭し、日常生活に自然に溶け込むAIの在り方を提示していきたいです。
――テオリア・テクノロジーズではどのような人材を求めていますか?
中沢:自発的に課題を発見して主体的に行動できる方が、テオリアのカルチャーに合っていると思います。
マネージャーがいない環境なので、自分でやることを見つけられない人だとつらい環境かもしれません。逆にベンチャーマインドを持って自ら手を動かす人にとっては、とても働きやすい組織です。
安藤:認知症という社会課題に対して、身近な問題として捉えられる当事者意識を持った方でしょうか。当事者意識を持って「どうにかしなきゃ」と思っている人が入社すると、活躍できる場がたくさんありますから。
――最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします
安藤:私が理想とするのは、フォワードデプロイドエンジニアとして、顧客の現場に直接入り込んで困っていることを聞き、作ったシステムでその解決策を提供する働き方です。こうしたアプローチに共感していただける方と一緒に働きたいです。
中沢:認知症という課題には、当事者のみならず介護従事者や家族など、さまざまな立場の方々が関わっておられます。こうした社会課題解決への想いを技術によって実現していく取り組みに、ぜひご参加いただきたいと思っています。
