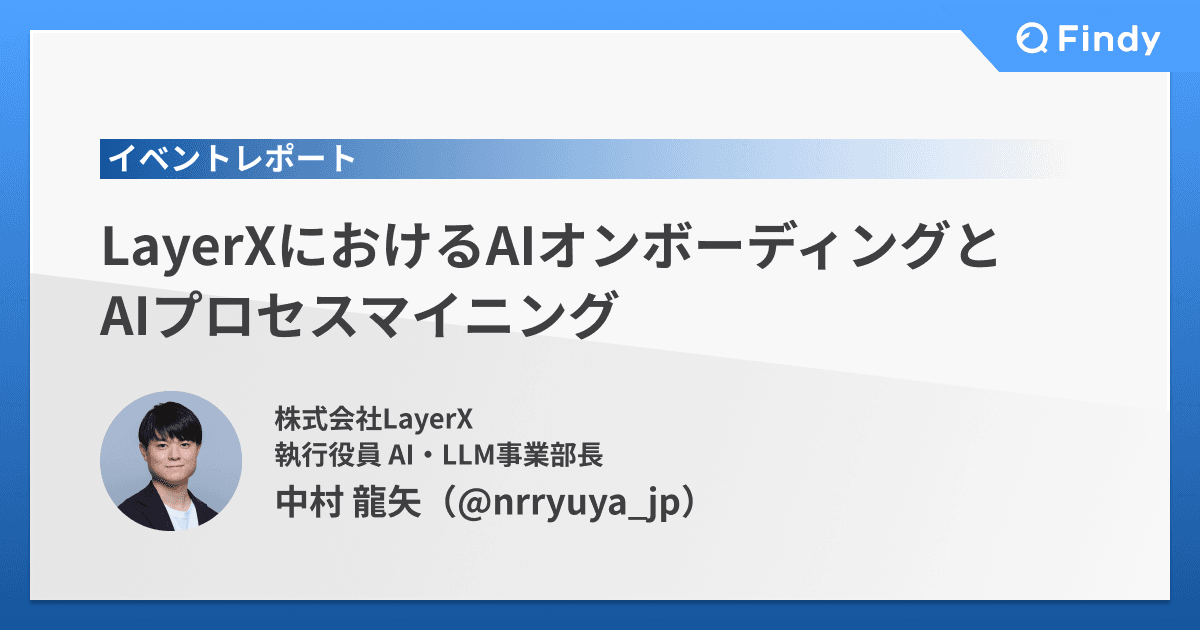本記事では、2025年5月28日に開催されたオンラインイベント「AIエージェントのオンボーディング-ヒトとAIの協同を支える”役割設計”とは」内のセッション「AIオンボーディングとAIプロセスマイニング」の内容をお届けします。同セッションでは、株式会社LayerXの中村龍矢(@nrryuya_jp)さんに、AIオンボーディングのコンセプトと取り組みなどについてお話いただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。
中村:本日は、AIオンボーディングとAIプロセスマイニングと題して発表します。株式会社LayerXの中村です。私は現在、LayerXでAI LLM事業の責任者をしています。元々はLLMが登場する前の機械学習エンジニアで、その後セキュリティ・プライバシー研究を経て現職に至ります。
LayerXでは、AIオンボーディングを行うためのプラットフォーム「Ai Workforce」という製品を出しています。特定の業務や業界に関わらず、文書処理業務であればAIが幅広く対応する製品です。すでに三菱UFJフィナンシャル・グループ様や三井物産様といった日本を代表するエンタープライズ企業にご利用いただいています。
AIオンボーディングに関しては、社内ではかなり前から話題になっており、昨年11月頃に私がAIオンボーディングに関するnoteを出しましたが、当時はまだあまり馴染みのない概念だったように思います。半年ほど経ち、800人近くの参加登録があるイベントを開催できるまでに至り、非常に感慨深いです。この後、具体的な事例も出てくると思いますが、私のパートではAIオンボーディングの一般的なコンセプトと、弊社での取り組みについてご紹介します。
なぜ今、「AIオンボーディング」なのか
LLMやChatGPTが登場した頃より、私たちは事業化に向け本格的に取り組んできました。あくまで感覚ではありますが、GPT-4やGPT-4oくらいまでのLLMは、軽い幻滅期にあったように思います。