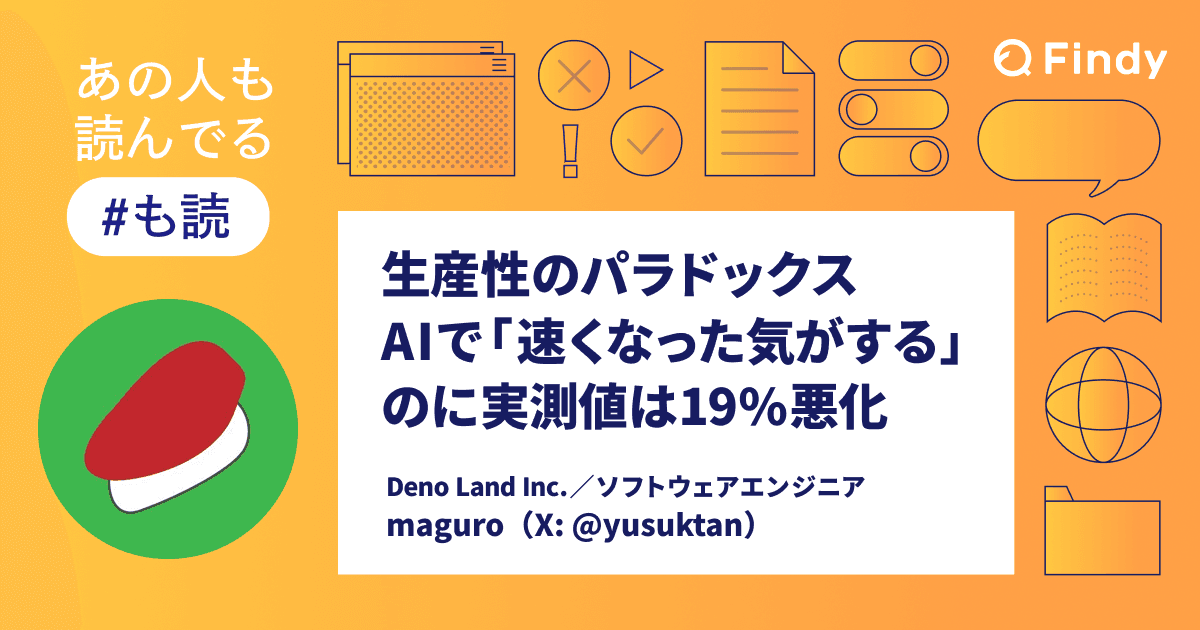「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
みなさんこんにちは。
「あの人も読んでる」、第10回目の投稿です。maguro (@yusuktan)がお届けします。
AIによって本当に生産性は向上しているのか?
数週間前からClaude Maxの月200ドルプランに課金しはじめて、Claude Codeを本格的に利用しています。
課金してから最初の数日はccusageを細かく眺めながら、毎日200ドルとか300ドルとかを使えることに快感を覚えていましたが、その後は数十ドルくらいに収まるくらいの利用にとどまっています。
Claude Code v1.0.44からはClaude Maxの定額サブスクリプションでのClaude Code Action利用が正式にサポートされるようになったこともあり、GitHub上で @claude のメンションを飛ばして具体的な処理の調査や新機能の実装方針の相談などをすることも多くなりました。この方法での利用分はccusageでは確認することができないのですが、いずれにしても月200ドルの価値は十分にあると感じます。