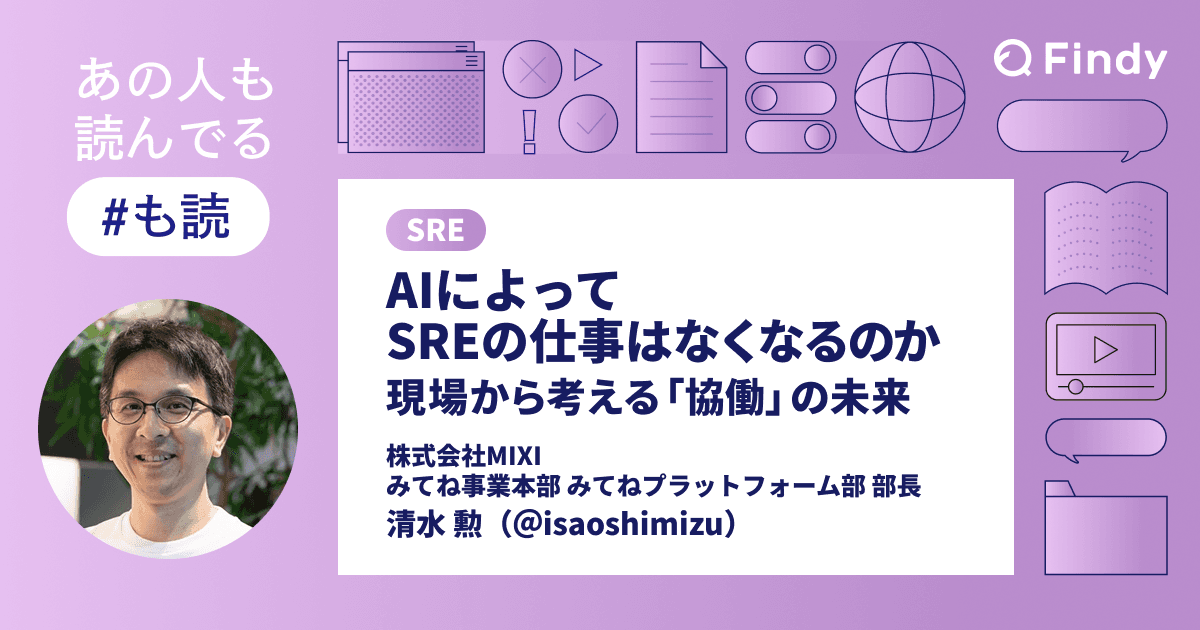「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
はじめに
こんにちは。清水(@isaoshimizu)です。
今回は、2025年9月27日に公開された記事「Report Finds LLMs Not Yet Ready to Replace SREs in Incident Management」(日本語訳:LLMはまだインシデント管理におけるSREの代替には至っていない)を読んで感じたことを紹介したいと思います。この記事は、The Adaptavist GroupのVP DevOpsであるMatt Saunders氏によるものです。
以前の「#も読」記事「The Future of Site Reliability: Integrating Generative AI into SRE Practices」でもSREと生成AIについて触れましたが、数ヶ月が経過し、AIの進化も激しい中、今回の記事ではさまざまな調査や実験を基に、SREにおけるAIの有効性をより具体的に考察した内容として、今回の#も読で取り上げることにしました。