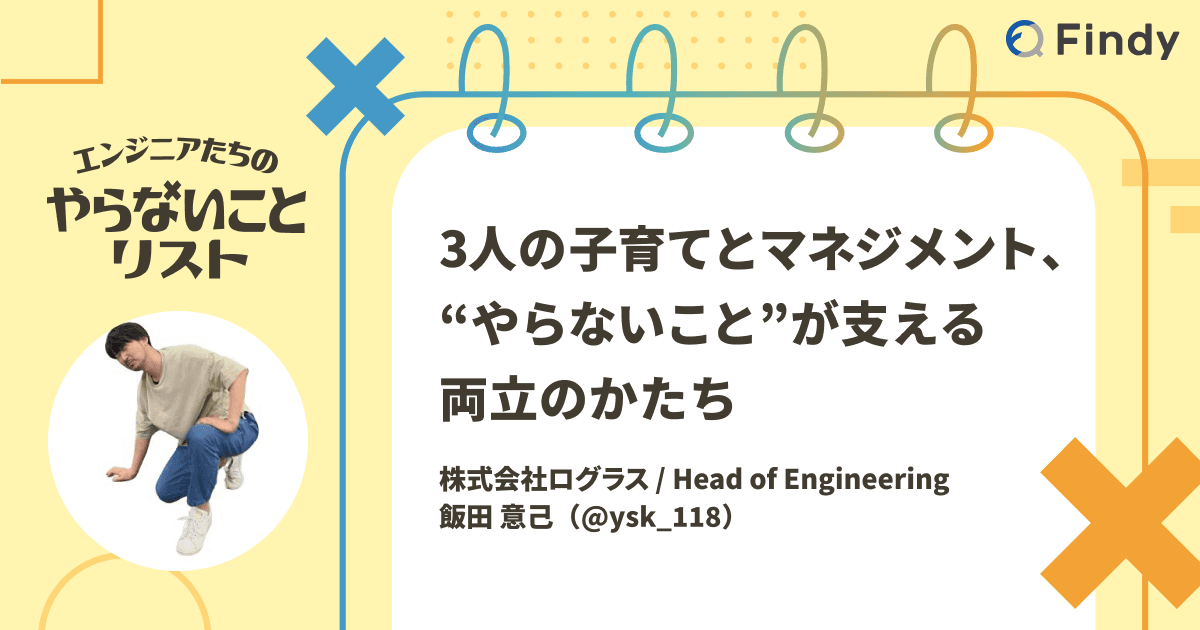「もっと成果を出さなきゃ」「スキルを増やさなきゃ」。そんな焦りに押され、やることを積み重ねていないでしょうか?けれど、本当に働き方を変えるのは“足し算”ではなく、“引き算”かもしれません。この企画では、エンジニアたちがあえてやめたことと、その後に訪れた変化をたどります。ムダをそぎ落とした先に残る、本当に大切な仕事や自分らしい働き方とは。誰かの“やらない選択”が、あなたの次の一歩を軽くし、前向きに進むヒントになりますように。
こんにちは、飯田意己(@ysk_118)です。現在、株式会社ログラスでHead of Engineeringを務めています。2020年にエンジニアとしてログラスに入社し、1人目のエンジニアリングマネージャー、VPoEを経て、現在の役割に至ります。
プライベートでは3人の子どもを育てる父親でもあります。朝6時半に起きて子どもたちと朝食をとり、保育園に送ってから出社。週の半分ほどは出社しており、出社する日は帰宅が遅くなることもあります。リモートの日は18時半頃に一度仕事を切り上げて、子どもたちと夕飯や風呂の時間を過ごす。そんな日々を送っています。
エンジニアとして、マネージャーとして、そして父親として。限られた時間の中で、私なりの「何をやらないか」についてお伝えできればと思います。
「やらない」を決めるのが苦手な自分
正直に言うと、もともとやらないことを決めるのは苦手です。この企画の趣旨に対してもあまりフィットしているとは言えない側の人間な自覚はあります。「やる」ことを増やして抱え込んでしまうこともこれまで多々ありました。
一方で、やりたいことが無限にある現実に対して、人間の時間は有限です。どう頑張っても「やれないこと」が発生してしまいます。なので、この有限の人間の時間をどのように使うか?という視点で考えられると、まあまあ悪くない判断ができるのではないかと考えています。
特に新卒1社目の頃、受託開発に関わっていた時期が最も「時間が足りない」と感じていました。顧客との納期がある中でドキュメントや開発の締切に追われる毎日で余裕がありませんでした。この頃は仕事の進め方や技術に関する知識も含め多方面的なインプットが必要な時期で、それこそがむしゃらに仕事をしていた時期です。
2社目以降は自社プロダクトの会社にいるため、納期は自分たちで決めて仕事を進めるという違いがあります。そのため稼働としては比較的コントロールしているつもりです。しかし、近年は組織マネジメントも含め、正解がない課題を扱うことが多く、また並行していろいろな課題に向き合うため、思考の負荷は高いと感じています。
もっと時間があれば余裕を持って思考できるのにと思うことはありますが、長く働いても思考の質は上がらないので、時間で戦うことの限界を感じることはあります。むしろ、その場その場での「やらない」ことも含めた意思決定が重要と感じています。
仕事において「やらない」と決めたこと
今やらないこと・自分がやらなくてもいいことを決める
マネジメントという業務の特性上、各ステークホルダーからの相談が集まりがちです。そういう意味でそもそも組織構造上ボトルネックになりやすい構造の中で仕事をしています。このような状況において重要になるのがネガティブケイパビリティという考え方だと思っていますが、今やらないという選択の不安に打ち勝つことで自身と組織の持続性を生み出すという捉え方も重要だと考えています。
また、自分が取り組んでいることを開示して、周囲の人から「これはあなたがやるべきではない」と言えるものはあるか?というフィードバックをもらうようにすると、意外と他の人に渡せる仕事が見つかったりします。
マネージャーになると人事に関連することなど開示しにくい課題も増えますが、定期的に何をしているかについて周囲からフィードバックを得るようにできると、思いがけないところで棚卸しが進んで楽になることもあります。
家族と過ごす休日、仕事のことを考えるのはやめた
どうしても自分に集まってきてしまう仕事を眺めた時、「土日にやるか…」と考えたことのある人も多いと思います。しかし、私の目の前には子どもたちがいます。
個人的な視点で仕事においてやらないと決めた大きなことは、休日に仕事のことを考えることです。
平日で遅くなることも多いため、その分休日は家族に脳のリソースを100%使うことにしました。仕事をしていなくても、どこか脳の片隅であのタスクどうしよう…と考えていると、目の前の家族に向き合いきれているとは言えないと思っており、そうした中途半端な状態ではどちらの幸せも実現できないと考えるようになりました。
今年の2月に育休を取得してからは、より一層このメリハリをつけることが大事だと感じるようになりました。
休日に勉強できない自分を責めない
どんな職種でも、社会が変化していく中で新しいことを学ぶ姿勢は重要です。休日に本を読んだり、新しい技術に触れてみたりする人も多いと思います。しかし、これも同様に現実には難しい状況もあるのではないでしょうか。
私の場合は、休日に勉強するということを「できなくても自分を責めない」と思うことにしました。
業務時間でやれる範囲をメインとし、休日に勉強できなかった自分に焦りを感じることをそもそも無くしたいと考えました。これも家族に向き合うための心構えとしてポイントになると考えています。
決断として難しいわけではないですが、本当にこのスタンスでいいのか?という迷いは常にあります。
日頃から新しい知識をどんどんキャッチアップしている若手のメンバーが多くいる中や、他社のマネジメントレイヤー層で学んだことを多く発信している人がいる中で、そうした投資を多くしていない自分がどう見られるのか?という不安は常に付き纏います。
一方で、周囲の人からは子どもが生まれて就業後の勉強会はあまり出れなくなった、というような話も聞くことがあります。おそらく皆さん悩みながら向き合われているところだとも思っており、人それぞれだとは思いますが、家族に向き合うという選択を間違ったと思うことはありません。
昨今はAIによって学習効率を上げることができたり、出社回帰の動きはありつつも、まだまだオンラインのイベントもあります。変化に適応しながらバランスが取れると良いと考えています。
家庭における「やらない」の意味
家庭では実はそこまでやらないと決めたことはなく、自分の時間の使い方として基本的に仕事の比重が高いため、家庭においてはやった方がいいがやれていないことの方が多い状況です。
つまり、「やらない」と決めるのではなく、「やれない」に対してどうバランスをとって家庭全体としての持続性をつくるか?という視点です。
人それぞれ異なると思いますが、完全に半々に分担する家庭もあれば、その比率が偏っていても別の部分でバランスをとっている家庭もあるでしょう。
パートナーとは支え合うための対話を
プライベートにおいては、基本的に家族から自分に対してやってほしいことの方が多い状況にあるため、仕事で取り組んでいることについて、自分がなぜそれをやる選択をしているのかを理解してもらうための努力をしています。
それが家庭でやらないことと釣り合うのかどうか?について、一方的ではなく感覚レベルで合わせにいくことは大事なコミュニケーションなのかなと考えています。私が「やれない」分、パートナーが「やる」ことになり、そこから生まれるパートナーの「やれない」ことがあるはずで、そうしたことをきちんと取り扱いたいと考えています。
2つの問いで「やること/やらないこと」を見極める
私が「やること/やらないこと」を判断する際の具体的な問いは以下の2つです。
自分にしかできないことは何か? 他の人にできるなら、自分がやらない選択肢が生まれる。
自分の人生にとって価値があるか? 自分の人生にとって価値を感じられなければ、やらない選択肢が生まれる。
このような視点で考えると、今価値が出せて今後も価値になる領域、もしくは今は価値が出せないが今後価値になる領域に投資しやすくなるのではないかと思います。場合によっては今後価値にはならないけど短期的には価値が出せるのでやる、という選択もできます。
逆に、今価値が出せない、今後も価値にならない領域についてはやらない、という選択がしやすくなるのではないかと思います。
罪悪感や焦りとの向き合い方
自分より圧倒的に知識を持っている人や、自分より圧倒的に大きな成果を出している人と相対した時に、やはり努力やコミットメントが足りていないのでは?という不安がないかと言われると嘘になります。
一方で、自分が経験していることや自分が出している価値に対しても、他の人にはない唯一無二のものがあると捉えられれば、実は不安に思う必要ないかもしれません。
おそらくこれは、そうした自分から見て自分よりすごい人と対話することでしか得られない視点であり、そうした人と「〇〇さんすごいですね」「ありがとうございます。でも、あなたのやっているところもあなたにしかできないですよね」みたいな会話ができると少し自信が持てるのではないかと思います。
相手から見て「こちらの芝が青い」と見えるのかどうか?はさまざまなスコープがありますが、
- 同じチームの中でやっている仕事が違っていて、異なる経験を積めている
- 同じ組織で異なるチームに所属していて、異なる経験を積めている
- 同じ会社で異なる部門に所属していて、異なる経験を積めている
- 異なる会社に勤めていて、異なる経験を積めている
というように、どのスコープで比較するのかによって変わります。このように置かれている状況が異なるさまざまな人と対話することで、何かを「やらない」選択をしていても、その分「やっている」選択に自信を持てる可能性があると思っています。
「やらない」から生まれた、心の余白
やらないことを意識したことによる最も大きな変化は、精神的な余白ができたことだと思います。
すべてをやらなければいけないと思い込むと、いくら時間があっても足りず、すべてに手を出していろんな人からの期待を裏切ることになってしまいます。精神的に追い詰められる前に「やらない」という期待値調整ができるようになったこと。それが大きいと考えています。
一方、こうした進め方や考え方が当初からできていたかというとそうではなく、冒頭に記載したような若い頃にがむしゃらにやった経験も今につながっていると思いますし、現在自分の役割に対して周囲で支えてくれる人がいて初めて成り立つものだと思っているので、単に「やらない」を決めればそうなるかというとそうでもないところがあります。
「やらない」を通して「やる」領域を見極める
私の場合、キャリアにおいてやらない(この道はない)と強く決めていることはありません。むしろ必要があればなんでもやるというスタンスで仕事をしています。
逆に言えば、どこかの道や何かの仕事に強くフォーカスし、経験を深めていくという領域の定めをしないようにしていると言えるかもしれません。
ある領域についてスペシャリストになっていくことはキャリアにおいても強みがあると感じますが、私のキャリアは割と初期の頃からその時々で必要なことをやるという積み上げ方をしてきたところがあり、ジェネラリストなキャリアになっています。特に尖りがない選択をしてきたことに対するコンプレックスはありつつも、逆にこれを強みとしてこれから先も仕事をしていく方が良いのではないかと感じています。
一方で、最近になって改めて思っていることは、自分の中で今価値が出せる領域をいかに手放していくか?です。
自身がこれまでの経験を持って今価値が出せる仕事というものは、どうしたらできるのか実は言語化も体系化もされていない仕事だったりします。これを思い切って「やらない」にしていかないと、結局「やる」が肥大化していき、プライベートとのバランスも保てなくなるかもしれません。
そうした持続性の観点でも、改めて「やらない」に向き合うことは大事なのだと気づかされました。
継続的に問い続けることで見えてくる、自分らしさ
前提としてキャリアなどを考えながら家庭との両立をすることは非常に難しいものです。その中で家族に向き合うという選択は何よりも大事なことだと思って欲しいと思います。
その中で「やらない」という選択で不安になるのではなく、「やる」選択をしたものにそれだけの価値があるかを振り返ってみると良いと思います。
もしそれだけの価値がないと感じたなら、「やる」選択と「やらない」選択をした内容を見比べて入れ替えてみても良いでしょう。周囲の状況次第で何を「やる」べきかは変わっていくはずです。
目の前にある仕事はそのほとんどが「やった方がいい」「あった方がいい」ものです。それゆえ、「やらない」と判断することには勇気がいりますし、不安にも駆られます。
ですが、有限のリソースをどう使うか。その問いに向き合い続けることが、自分らしいキャリアと家庭の両立につながっていくのだと思います。
あなたは今、何を「やる」と選び、何を「やらない」と決めますか?