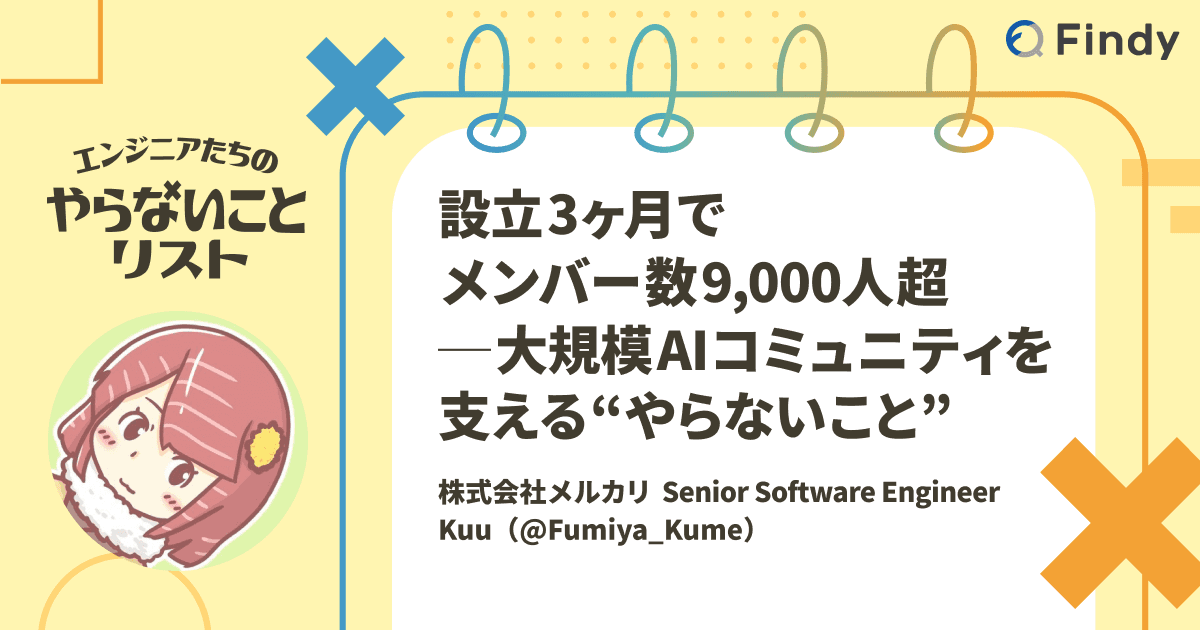「もっと成果を出さなきゃ」「スキルを増やさなきゃ」。そんな焦りに押され、やることを積み重ねていないでしょうか?けれど、本当に働き方を変えるのは“足し算”ではなく、“引き算”かもしれません。この企画では、エンジニアたちがあえてやめたことと、その後に訪れた変化をたどります。ムダをそぎ落とした先に残る、本当に大切な仕事や自分らしい働き方とは。誰かの“やらない選択”が、あなたの次の一歩を軽くし、前向きに進むヒントになりますように。
こんにちは、Kuu(@fumiya_kume)です。株式会社メルカリでSoftware Engineerとして働いており、新卒入社から6年目になりました。社内ではAI活用推進担当として活動しながら、AIAU(AI Agent User Group)というコミュニティでAI関連イベントの運営に携わっています。
AI技術の進化スピードは凄まじく、毎日のように新しいツールやサービスが登場しています。そんな激動の時代にAIコミュニティを運営していると、「あれもやりたい」「これも必要だ」という思いに駆られます。
しかし、本業を持ちながら趣味としてコミュニティ運営に携わる中で気づいたことがあります。それは「やらないことを決める」ことの重要性です。
AIAUとは?大規模AIイベントを有志で運営するコミュニティ
AIAUは、AIエージェントに関する情報交換、学習、交流を目的に、2025年4月に発足したコミュニティです。現在は約10,000名が参加する大規模なコミュニティへと成長し、普段はDiscordで情報交換を行い、最新のAI技術について議論を深めています。2025年6月に開催したCursor Meetup Tokyoでは、初回イベントにもかかわらず約6,000名の方にご参加いただきました。その後もDevin Meetup Tokyoをはじめ、AI関連の大規模イベントを開催してきました。
とはいえ、運営メンバーは全員が本業を別に持つ「イベント運営のアマチュア」です。最近では本業でもAI推進を担当するメンバーが増えてきましたが、基本的にはプライベートの時間を使って活動しています。
理想を言えば、完璧な運営体制でイベントを開催したいところです。しかし現実には、限られたリソースの中で妥協点を見つけつつ、参加者も運営も楽しめるイベントをつくることが大切です。
続けるためにあえて“やらないこと”を選んだ理由
運営メンバーが楽しんでイベントに関われること。 これが継続的なコミュニティ活動の鍵だと気づきました。
誰かが犠牲になるのではなく、全員が余裕を持って運営に参加できる状態をつくる。そのためには、思い切って「やらないこと」を決める必要がありました。
今回は、AIAUの運営において「あえてやらないこと」を3つ決めました。
- 受付対応
- 登壇者選定
- 細部へのこだわり
次の章から、それぞれ「なぜそうしたのか」「どう実践したのか」「どんな結果があったのか」を紹介します。
やめたこと1: イベント受付時間の柔軟な対応
なぜやめたのか
本音としては、遅刻してきた参加者にも柔軟に対応したいところです。しかし、イベント開催中に受付を担当し続けることには、大きな問題がありました。
- 受付担当者がイベントに参加できない
- 時間通りに来た参加者との間に不公平感が生まれる
- 運営リソースが分散してしまう
どう実践したか
受付時間を「開場時間+5分」と明確に設定し、それ以降は受付を撤収する運用にしました。もちろん、参加者には、イベントページやSNSを通じて事前にしっかりと告知しています。
結果どうなったか
実施してみると、体感では約95%の参加者が時間内に受付を完了し、イベントを楽しんでいただけています。そして何より、運営メンバー全員がイベントに参加し、登壇内容を聞き、参加者と交流できるようになりました。
5%の遅刻者のために、運営の誰かがイベントに参加できない状況は避けるべきだと確信しています。日本の人が持つ「おもてなし精神」も大切ですが、時には思い切った判断が全体の幸福度を高めることもあるのです。
やめたこと2: イベント登壇者を全部運営が決めない
なぜやめたのか
イベントの質を左右する登壇者の選定。従来は運営メンバーのネットワークだけで登壇者を探していましたが、これには限界がありました。
- 発表内容が似通ってしまい、多様性が失われる
- 新しい人や情報が入ってこなくなり、コミュニティが停滞する
- 隠れた知見やユニークな視点を持つ人に出会う機会を逃してしまう
そして何より、「誰に登壇してもらうか」という議論に、想像以上の時間とエネルギーを使っていました。それは運営リソースの観点から見ても、タイムパフォーマンスが悪いと感じていました。
どう実践したか
イベントの方向性を示すキーノートスピーカーは事前に決めつつ、それ以外の登壇枠は公募制に切り替えました。
公募の方法は、今も試行錯誤中です。TwitterのDMは重要な連絡が埋もれてしまうため避け、現在はGoogleフォームで募集することが多くなっています。
結果どうなったか
予想以上の効果がありました。MCP Meetup Tokyoでは、運営メンバーの想像を超える実用的なプロポーザルが集まり、イベントの質が大きく向上しました。
例えば、金融系の事業会社にてMCPを活用している事例を聞けたりと、運営だけでは想像しきれない多様な視点・テーマが集まりました。
結果として、既存のネットワークの外から、新鮮で実践的な知見を持つ登壇者が現れるようになったのです。コミュニティの多様性も高まり、参加者からの評価も上がっています。
実際にあった参加者からの声として、
「さまざまな立場(プロダクトマネージャー、開発者、SIerなど)からの話を聞けた」
「実装に偏らず、ビジネスサイドと技術サイドの話がバランス良く聞けた」
などの感想が寄せられました。
運営側が選ばないことで、結果的に “より豊かなコミュニティが育っていく” そんな手応えを感じています。
やめたこと3: 重要なところ以外に時間をかけない
なぜやめたのか
イベントページの空白になってる部分を決めるための議論が長引き、イベント公開が遅れることがよくありました。細部にこだわるあまり、本質的でない部分に時間とエネルギーを消費していたからです。
どう実践したか
イベント開催において、本当に必要な要素を2つに絞りました。
1. イベントコンセプト
- 世間の興味関心とマッチしているか
- 1次情報(Headquarterの人など)を提供できるか
- 参加者にとって価値があるか
2. 会場探し
- イベントコンセプトに興味を持ちそうな企業にアプローチ
- 該当技術を活用・提供している企業なら話がスムーズ
この2つが決まれば、日程や規模感は自然に決まります。懇親会スポンサーなど「あったらいいもの」は、最悪なくても開催できます。
結果どうなったか
イベントの企画から公開までの期間が大幅に短縮されました。そして節約できた時間とエネルギーを、イベントの独自性や新しいチャレンジに投資できるようになりました。“必要十分なライン”を見極めることで、運営全体がぐっと軽くなりました。
「とりあえず公開して、改善していく」というアジャイルな運営スタイルを取り入れたことで、変化の激しいAI領域でも、継続的にイベントを円滑に開催し続けることにつながっています。
コミュニティ継続のカギは、“見直す柔軟さ”と“やめる勇気”
これらの「やらないこと」は、一度決めたら終わりではありません。コミュニティの成長やメンバーの変化に応じて、定期的に見直していく柔軟さが必要です。
数ヶ月が経過した現在、これらの判断は正しかったと感じています。運営メンバーの負担は減り、イベントの質は向上し、何より運営自身が楽しんで活動できるようになりました。
本業を持ちながらコミュニティ運営をする場合、すべてを完璧にこなすことは不可能です。だからこそ、「やらないこと」を明確に定め、粛々と運用していくことが重要なのです。
簡略化して生まれた“余白”は、イベントのコンセプトづくりや、今までにない面白いチャレンジに使うことができます。その余白こそが、コミュニティの独自性と持続可能性を生み出すのかもしれません。
あなたのチームやコミュニティでは、どんな「やらないこと」を決めていますか?一度立ち止まって、本当に必要なことと、思い切ってやめられることを整理してみてはいかがでしょうか。
完璧を求めるのではなく、余白を持つ勇気。
それが、持続可能で楽しいコミュニティ運営の第一歩なのかもしれません。