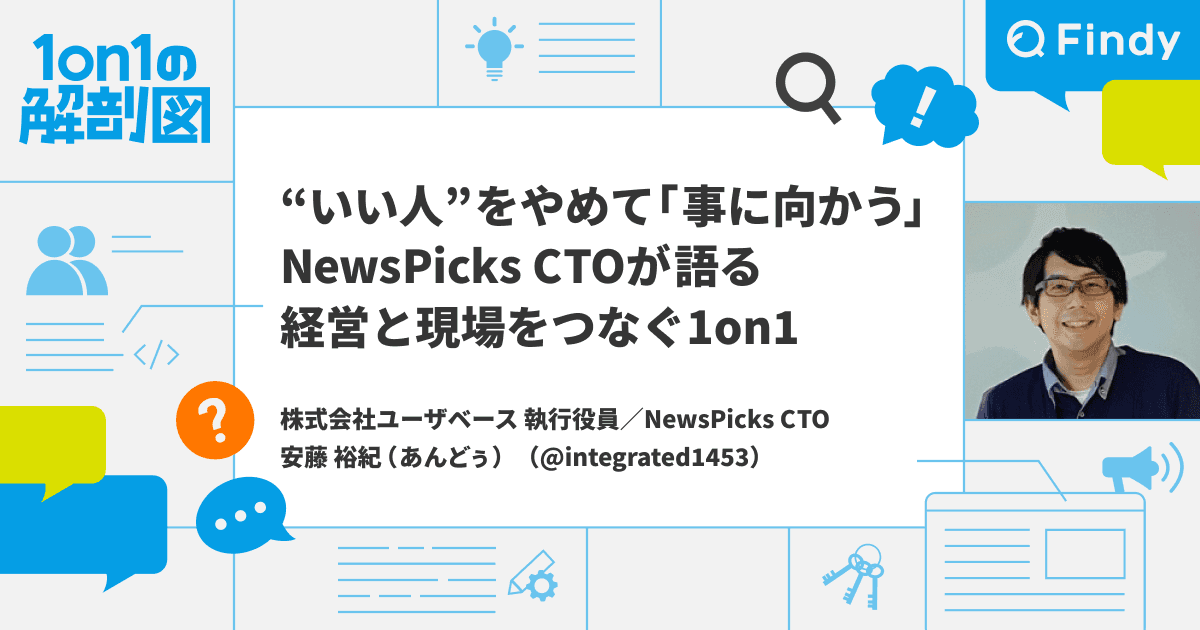部下の成長促進や信頼関係の構築といった効果が期待される1on1ミーティング。しかし、そのノウハウを体系的に学べる機会は少なく、手段が目的化したり、実施者によって対話の質がばらついたりする課題も見られます。
1on1に絶対的な正解はない中、本連載「1on1の解剖図」では、様々な領域で活躍するエンジニアの「1on1の手法」に焦点を当て、現場の課題や気づき、乗り越え方を掘り下げます。
第2回は、株式会社ユーザベース 執行役員/NewsPicks CTOの安藤裕紀(あんどぅ)氏(@integrated1453)。2021年にSREチームのシニアエンジニアとしてユーザベースに入社し、同チームのリーダー、シニアEMを経て、2025年1月にNewsPicks CTOに就任。現在は計15人ほどのチームリーダーやメンバーと週1~隔週で1on1を実施しています。
長年SRE領域で活躍し、もともとピープルマネジメントへの関心は高くなかったという安藤氏。1on1の試行錯誤や企業文化の反映に加え、AI時代の新人エンジニア育成、キャリアの転換点なども聞きました。
誰のためにもならなかった、“いい人”であろうとする姿勢
──過去のnoteでは、1on1を「目標達成に向けた日常的な問題解決の場」と表現されていました。この考えに至るまでに試行錯誤があれば、教えてください。
SREチームのリーダーになって間もない頃は、メンバーにとって“いい人”であろうとしていました。メンバーの成長を手助けしようと、やりたいことを聞き出し、サポートに徹する姿勢をとっていたんです。しかし、それではチームの成果に結びつきませんでした。
その結果、「メンバーはこういう業務をやりたがっているので、うちのチームの仕事はここまでです!」と線引きし、「組織とチームの対立構造」を生んでしまったこともあります。これは、マネージャーとして一番してはいけないことでした。
現在は、「どうすれば組織におけるチームの成果を最大化できるか」という視点のもと、1on1の相手に期待する役割や、達成すれば成長につながることを伝えています。いわば、組織の視点を“翻訳”するイメージですね。
相手のスキルや行動に課題があれば、厳しいフィードバックも行います。こうしたアプローチによって「チームの成果」と「個人の成長」の両方が進み、1on1の意義も増すと考えています。
──個人の要望ばかりを聞くのではなく、チームのゴールを個人目標に落とし込む手法に切り替えたのですね。この転換は、どのようにして実現したのでしょうか。
『エレガントパズル エンジニアのマネジメントという難問にあなたはどう立ち向かうのか』(日経BP、2024年)を読んだとき、「マネージャーに最も誇らしいときを尋ねたら、誰かの成長を支援したときの話を語ってくれるだろう」という一文に出会いました。
そこから「組織に貢献できるエンジニアに成長してもらう」という“自分自身が事に向かう”姿勢が大切だと気づき、メンバーにいい顔をして一時的に気持ちよくなってもらうのではなく、成長を後押しし、最終的に感謝してもらうことを目指すようになりました。
「あの会議での発信、どう思った?」でメンバーと視点を共有
──ユーザベースは全社共通の価値観「The 7 Values」など、独自の企業文化を掲げている印象です。1on1をはじめとするマネジメントに反映していることはありますか。
企業文化はかなり反映していますね。The 7 Valuesを実現するための具体的な行動指針「34の約束」を基に、1on1などのマネジメントを行っています。この行動指針では、各バリューにおいて「DON’Ts: すべきでないこと」「DO’s: すべきこと」を示しています。
例えば、Value 1の「自由主義でいこう」では、DON’Tとして「管理をゆだねる」、DOとして「自己規律する」があります。1on1で相手にフィードバックを行う際は、「この行動は、DON’Tに振れてしまっているように見える」など、34の約束に基づいて客観的に伝えるようにしています。
──安藤さんならではの1on1の工夫があれば、教えてください。
全社ミーティングなどで経営層が話したことについて、「どう思った?」と考えを聞くようにしています。こうした情報は一方的な発信のままだと「自分の仕事には関係なさそう」と聞き流されてしまいがちですが、マネージャーの視点から発言の背景を補足することで、メンバーは自分の仕事とつなげて考えられるようになります。
例えば「あの発言は事業の伸びしろを示唆していて、それはエンジニアリングで実現できるかもしれない」と伝えれば、メンバーにとって気づきになるはずです。逆に、メンバーから「現場の実情とはズレている気がする」「そもそも何の話かよく分からなかった」といった意見が挙がることもあり、経営層の意図が現場に伝わっているかを確認できます。
こうした“視点の交換”を通して「こう動いたら事業成長に貢献できるのではないか」「じゃあ、次の四半期はこういう目標設定にしてみようか」といった行動変化につながることもあり、各メンバーのモチベーションや自己効力感にも影響すると感じます。私自身、経営層の発信などをメモして考えを整理しておき、1on1での話の種にしています。
混沌とするAI時代の新人育成。最初に学んでもらうことは?
──CTOの立場では、メンバー層の状態を把握するためにチームリーダーやEMとの連携も求められると思います。工夫していることはありますか。
確かにEMとして直接見ているチーム以外はチームリーダーを挟んでいるので、どうしても間接的な関与になりますね。そのため、「新卒メンバーCTO座談会」を月1回開催し、新卒社員に業務の進捗状況、前回からの成長や気づき、仕事の悩みや疑問などを共有してもらっています。
こうした取り組みを通じて、自分が直接見ていないチームの中でも、新卒のような組織のメッセージが届きづらい層に、どれくらい意図が伝わっているかを確認しています。
──この座談会は、安藤さんが主導して実施しているのでしょうか。
はい。個人的に必要性を感じ、実施しています。新卒1~3年目ぐらいの時期は、今後のキャリアの成長角度を決定づける重要なタイミングです。仕事の経験や機会は資産のように福利で積み上がるので、月次でトラッキングしています。成長に苦戦や停滞が見られた場合はチームリーダーに働きかけ、新たな挑戦機会を打診したり、前向きに仕事に取り組めるようコミュニケーションを見直したりしてもらっています。
この取り組みは「組織の底上げには、若手の成長が不可欠である」という課題意識から始めましたが、結果として「経営メッセージや事業状況が現場に届いているかどうか」「それに納得して仕事ができているか」を確認するきっかけにもなっています。
──最近、AIコーディングエージェントなどの普及により「ジュニアレベルのエンジニアに任せる業務が減っている」という話もあります。AI時代の新人育成で工夫していることはありますか。
私の場合は、「人間にしかできない3つの役割」を意識してもらうよう伝えています。具体的には、(1)現場での「空気感」や非デジタルな情報の収集、(2)正解のない世界での意思決定、(3)結果に対する責任を取ること──があります。
例えば、当社は撮影スタジオを擁しており、そこから動画配信を行っています。撮影機材がAWS環境に接続されている物理的な状況を知りに行く、現場のスタッフと話して映像制作の課題を把握する、課題を整理して「こういうプロダクト開発をすれば解決できるのでは」と仮説を立てる、実行して結果に責任を持つ。これらはどれも、AIには難しいことです。
こうした領域から学び、そのうえでコーディングや実装スキルなど足りない部分を身につければ、「AIにはできない部分で価値を出せるエンジニア」として成長できるはずです。「全てのエンジニアがAIのマネージャーになる」と言われる中、人間はAIが知らないことを教える側に立つ必要があるので、まずはそうした情報を取りに行き、結果に責任を持つ動きをしてもらいます。
“事に向かう”姿勢が、メンバーに伝わった
──1on1で部下の成長につながった手応えや、言われてうれしかった一言はありますか。
EMとして初めてSRE以外のチームを率いた際、現場の専門知識には詳しくないながらも、四半期のチーム目標を達成し、チームへの高評価やメンバーの昇進につなげました。
その際、メンバーから「安藤さんがリーダーを務めてくれたおかげで、チームの目標と進むべき方向がはっきりし、事業や組織の役に立つ仕事ができている実感を持てました」という言葉をもらい、すごくうれしかったです。
昔は専門外のチームもまとめるという意味で、EMを「技術力の伴わない、うさんくさい仕事」だと感じており、「自分はやりたくないな」と思っていました。しかしこの経験から、EMには明確な専門性があり、その役割でも成果を出せると気づくことができました。
キャリアの転機で考えたのは「求められることで成果を出したい」
──マネジメント全般の話も伺いたいです。お話しされていたEMへの印象に加え、過去の発信から、もともとピープルマネジメントへの関心が強いわけではなかったとお見受けしました。マネージャー職への道筋が見えたとき、どのような心境でしたか。
「エキスパートになりたい」という思いはありましたね。最初にEMとして複数チームを見てくれないかと打診されたときは、「SREチームでエンジニアとしてスキルを高めながら、業界の第一人者としてのプレゼンスを高めていきたい」と伝えました。
しかし、「安藤のSREチームはうまくいっているから、他のチームも任せてみたい」と頼まれたとき、「できるかどうかは分からないけど、やってみようか」と思い、引き受けました。SREのエキスパートに対する思いも残っていましたが、自分がやりたいことより、組織に求められている部分で成果を出すことを優先するのがプロであると考えたためです。
──マネージャー職に進み始めた頃のご自身に一言声をかけるとしたら、何と伝えますか。
「大きな課題を解決しようとすると、結局は全部やらなきゃいけないから、やってみたらいいんじゃない?」ということですね。『スタッフエンジニア マネジメントを超えるリーダーシップ』(日経BP、2023年)を読んだとき、スタッフエンジニアにもプロジェクトマネジメントやステークホルダーマネジメントが求められると気づきました。
実際、大規模な課題解決をしようとすると、技術専門職であっても、チームの枠を超えた「調整・交渉・合意形成」のプロセスは必要不可欠です。ピープルマネジメントに関しては「人の評価者にならない」という意味では避けられるかもしれませんが、当時の自分には「人の評価や成長支援も背負うことで、組織の中でより大きな問題解決ができるのでは?」と言ってあげたいですね。