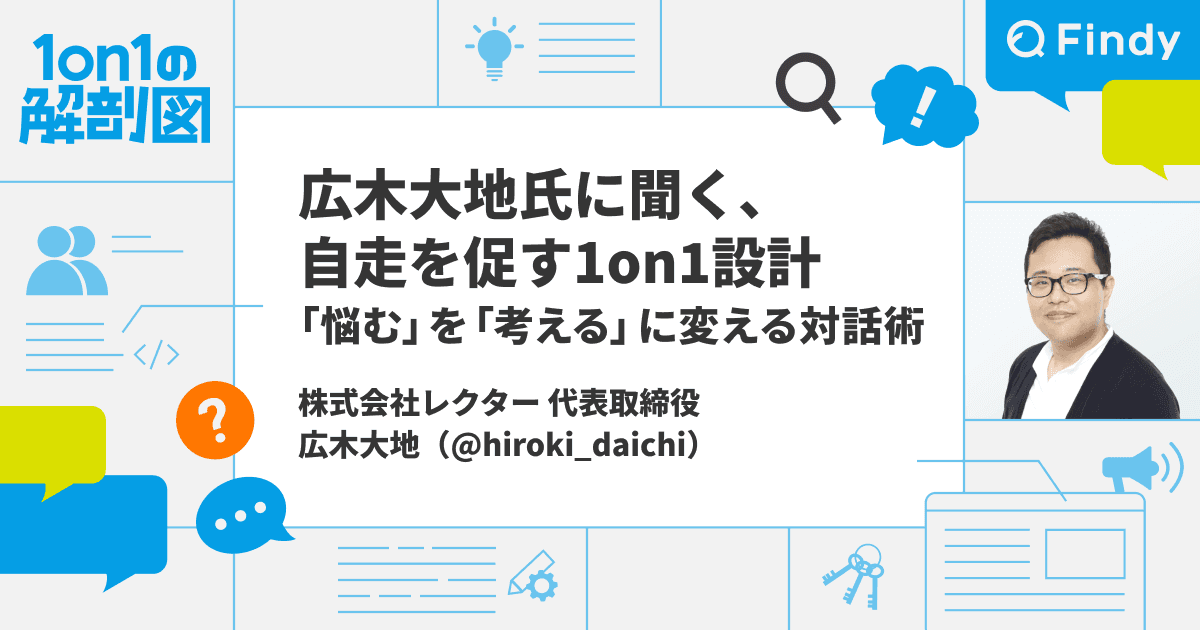部下の成長促進や信頼関係の構築といった効果が期待される1on1ミーティング。しかし、そのノウハウを体系的に学べる機会は少なく、手段が目的化したり、実施者によって対話の質がばらついたりする課題も見られます。
1on1に絶対的な正解はない中、本連載「1on1の解剖図」では、様々な領域で活躍するエンジニアの「1on1の手法」に焦点を当て、現場の課題や気づき、乗り越え方を掘り下げます。
第1回に登場いただくのは、株式会社レクター 代表取締役の広木大地氏(@hiroki_daichi)。著書『エンジニアリング組織論への招待』(技術評論社、2018年)や、Web連載「いまさら聞けないソフトウェアと組織の新常識」を通して、1on1を含むエンジニアリング組織のマネジメント論を発信しています。
企業の技術経営アドバイザーを務め、EMやテックリード、CTO、経営者など、社内外の様々な立場の人々と1on1を行う同氏。今回は、広木氏が考える1on1の意義や運用のコツ、陥りがちな落とし穴を聞き、現場で試せるヒントとしてお届けします。
1on1はやめてもいい。広木氏が思う役割
──チャットや定例会議など、社内のコミュニケーション手段は多様化していますが、その中で1on1はどのような役割を担うべきだと思われますか。
1on1はチャットや定例会議と同列で捉えられがちですが、本来の役割は全く異なります。1on1は近年流行りすぎており、目的が曖昧なまま形骸化している傾向があると思います。マネジメントスキルや部下との信頼関係が十分に育っていない段階で「隔週でやりましょう」と頻度だけを決めても、お互いに何を話すべきか分からず、あまり意味がありません。「やるものだからやる」となっているなら、やめてみるのも一つの選択肢でしょう。
僕にとって1on1とは、長期的な課題や悩みを抱え、泥沼にはまっている相手に対し、“泥からレンガを作って積み上げる”ように思考の整理を手助けする場です。進捗状況の共有や業務上の提案・承認は、持ち込むべきではありません。そうした運用を続けていると、部下は「今度の1on1で話せばいいか」と考え、業務の進行が遅れてしまいます。まずは、必要な時にすぐ話せる関係性を築くべきです。
他者という“不確実性”にどう向き合うか
──広木さんは様々な媒体で「不確実性へのアプローチ」について発信されてきましたが、1on1ではどのような不確実性があるとお考えですか。
1on1における最大の不確実性、というか理解しておくべき出発点は「自分と他人は別の人間だ」ということだと思います。部下の課題は本人にしか解決できず、上司が代わりに解いてあげることはできません。「きっと仕事ができるようになりたいはず」「成果が出ていなければ落ち込んでいるはず」「だから自分からのアドバイスを求めているはず」と思い込んで接すると、コミュニケーションが一方的になってしまい、部下にとってはつらい時間になりがちです。
──それに対して、どんなアプローチが有効だと思われますか。
僕は、自分自身が“広めの作業台”になることを意識しています。相手のふわっとした話を、対面ではホワイトボードに、オンラインではメモに書き出して少しずつ可視化していきます。すると、相手は僕の顔色ではなく、書かれている内容に意識が向き、自分が抱えている課題の構造が見えてくるのです。
そこで僕が「ここはどうなっているの?」と、書かれていない部分について質問すると、相手は説明するうちに自分の無意識の前提や思考フレームの外側に気づき、これまで見えていなかった全体像が徐々に浮かび上がります。相手の頭の中にあるものを全部取り出し、作業台に並べることで、その場でひらめいて解決してもらえることもあれば、まずは考えられる選択肢や判断基準がはっきりすることもあります。
──相手の意識を、自分ではなく書かれている内容に向けるのですね。
ええ。1on1では、僕を見てもらう必要はあまりありません。自分自身が向き合うべき内容のほうを見てもらいます。
「悩む」から「考える」へ。初期設計と着地点
──過去の発信では、1on1でキャリアの話に入る前に、まず健康やストレス、交友関係など、身近な不安を解消するための会話をすることを勧めていましたね。
多くの人が「1on1ではキャリアの話をするものだ」という先入観を持っていると感じます。僕の場合、初期の1on1では丸々お互いの話をします。信頼関係ができていない段階で「最近仕事どう?」と聞いたら、部下は「ここで『悩んでいる』と言ったら評価に響くのかな」と不安を抱き、なかなか本音を言えないかもしれません。
だからこそ、まずは「あなたに関心を持っています」「私はこういう人間で、味方ですよ」というメッセージを示すことが大切です。両者の安心感があって初めて、キャリアなどの本題について話せると考えています。
──1回の1on1を終えた時に、どのような状態になっているのが理想的でしょうか。
1on1を受ける側が「楽しかったな」「少し目が覚めたな」「次はこうしよう」などと思えれば、十分だと思います。僕はよく「“悩む”と“考える”は違う」という話をしています。
“悩む”は同じことを考え続けても解決策が出ずに疲弊している「状態」ですが、“考える”は「これを調べてみよう」「◯◯さんに聞いてみよう」と、次にすべきことが決まっている「行動」です。そのため、僕は相手の“悩む”を“考える”に変換する手伝いをしています。相手の悩みという泥を固めてレンガを作り、積み上げて道を舗装していくイメージです。
解決策の提示ではなく、視点を増やして自走してもらう
──マネジメント職に就いたばかりの方は「相談を受けても“共感”で終わり、解決策を提示できない」という悩みを抱えるケースもあります。解決策を与えるより相手が自分で答えを見つけられるよう導くことが重要だと思いますが、1on1を行う側が円滑に進めるためのコツはありますか。
仕事に限らず、相談してきた人が必ずしも解決策を求めているわけではありません。重要なのは、“自分の頭を貸している感覚”です。共感というのは、相手の発言を繰り返すだけでも成立します。例えば「つらかった」と言われたら「つらかったんだね」と返せば十分で、逆に「私もつらかった!この前も……」と自分の話にすり替えてはいけません。
そのうえで「今話した以外に方法はあるんだろうか?」「その施策だと、お客さまにはどんなメリットがあるんだろう?」といった問いを投げかけ、相手の視点を増やしてあげます。こうしたやりとりを通して、相手は次第に「まずはお客さまのことを考える」と僕のメッセージを自分自身で繰り返せるようになっていきます。
──最近は生成AIに仕事の相談をする人も増えていますが、解を与えるよりも視点を増やすことは、人間のマネージャーが得意とする部分かもしれません。
そうですね。AIである程度可能なこともある中、僕としては「人間だからこそできること」を重視しています。本来自分でやれば済む業務を他人にやってもらうのは、課題を発見し、解決できる人材になってもらいたいからです。そうした意味で、マネジメントの醍醐味は「相手が自分で動いてくれるようになった時」だと思います。
1on1では、社員個人のキャリアアップや幸福の実現も大事ですが、会社が給料を支払っている以上、自社の成果に寄与しなければいけません。今の平均在職年数を考えると、10年単位での成長を目的に社員教育を行っても、自社のメリットにつながらない場合もあります。だからこそ、短期間で自走して課題解決できる人材を増やし、さらに難しい課題に取り組んでもらう必要があります。
実は社内の人は皆味方。1on1を受ける側の心構え
──ある意味、マネージャーの存在を不要にするのがマネジメントともいえますね。そのうえで、1on1は行う側だけでなく「受ける側の心構え」も重要だと思います。受ける側としては、どのような意識や準備が必要でしょうか。
大切なのは、「会社の人間は皆味方である」という意識を持つことだと思います。本来は同じ船に乗って共通の目標に向かっているはずなのに、視野が狭くなると上司や同僚が敵のように見えてしまうことがあります。しかし「1on1なんて面倒くさい」「どうせ言っても伝わらない」と思いながら仕方なく参加していては、そうした状況から抜け出せません。
1on1は、他者との対話を通じて自分の考えを整理したり、会社全体の視点を増やしたりできる貴重な機会です。楽しくないことではなく、価値を提供するためにはどこかで必要になります。そうした機会を生かさないと、仕事はつまらないままで、顧客に対して価値のあるサービスや製品を届けることも難しいでしょう。
これまで述べた通り、1on1を行う側は「あなたの味方ですよ」というメッセージを示すことが重要であり、受ける側も「社内には信頼できる人がたくさんいるんだな」と素直に受け止める姿勢が大事です。そのうえで、どうしても心理的安全性を確保できないのであれば、転職も一つの選択肢なのかもしれません。
AI時代は、自走力の向上が一層重要に
──広木さんのマネジメントノウハウは、既に確立されている印象です。トレンドやITツールが変化する中で、最近関心のあるトピックや取り入れたいことはありますか。
単純な作業はAIにある程度任せられるようになってきている中、課題に直面した際に長期間行き詰まったり、過度に感情的になったりするような「自走できない人」を、マネージャーが時間をかけてケアすることは、会社にとって得策ではなくなると思います。世の中の変化に伴い、われわれもやり方を変えていく必要があります。
その時に問われるのは、社員一人ひとりがセルフメンタリングを行い、前向きな状態を作れるかどうかです。そのため、日々の1on1でも「お互いの了解のもと、どこまで自走できるようにするか」という視点が重要になります。
これは、今回一貫してお話してきたテーマです。1on1をせずに済むならそれに越したことはありませんが、行うのであれば大きな目標の実現に向けて課題や悩みを話せる場にすべきだと思います。だからこそ、最近は「相手の自走力をどのように高められるか」に関心を持っています。