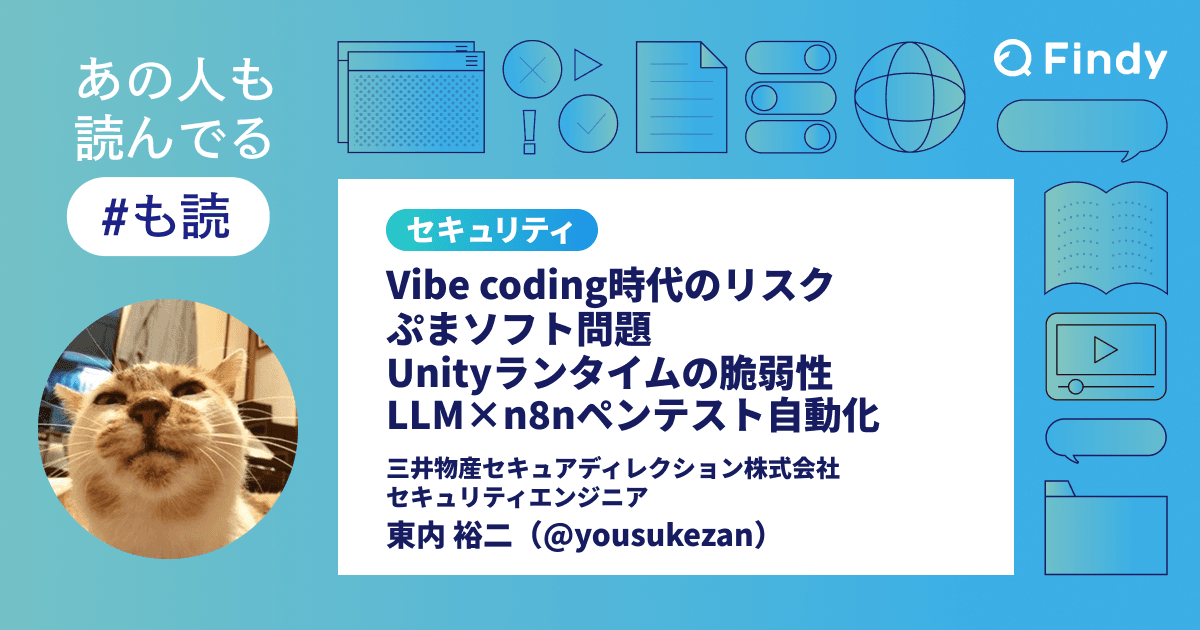「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
こんにちは。東内(@yousukezan)です。
相変わらず引きこもってAIとセキュリティの記事を中心に読んでいます。ようやく秋らしくなってきましたが、季節とは裏腹にセキュリティの世界ではアサヒグループホールディングスやアスクルがランサムウェアで被害を受けるなど、まったく落ち着きません。それでは、最近読んで良かったコンテンツの一部を紹介します。
Vibe coding時代に抑えておきたい5つのセキュリティリスク
AIアシスタントがコード生成を主導するVibe codingスタイルの開発手法が注目されています。筆者も幾つかのアプリをVibe codingで作成していますが、生成結果を無条件に実行するのは危険だと感じており、注意して使うようにしています。本記事では、AI主導開発環境において見過ごされがちな5つのセキュリティリスクを具体例とともに整理しています。
例えば、AIによって生成されたコードに秘密鍵やAPIキーが埋め込まれてしまう可能性、プロンプトや補完の流れを悪用したプロンプトインジェクションによる挙動の逸脱、依存ライブラリの脆弱性やサプライチェーンリスク、入力値のバリデーション不備、ログや例外処理の抜けによる情報漏えい、「AIに任せた結果の責任は誰が負うのか」という倫理的課題などが挙げられています。
これらのリスクに対して、プロンプト設計の工夫、ガードレールの導入、静的解析や二重チェックといった対策が解説されており、AIと人間の責任分担をどう設計すべきかを考える良い材料になります。