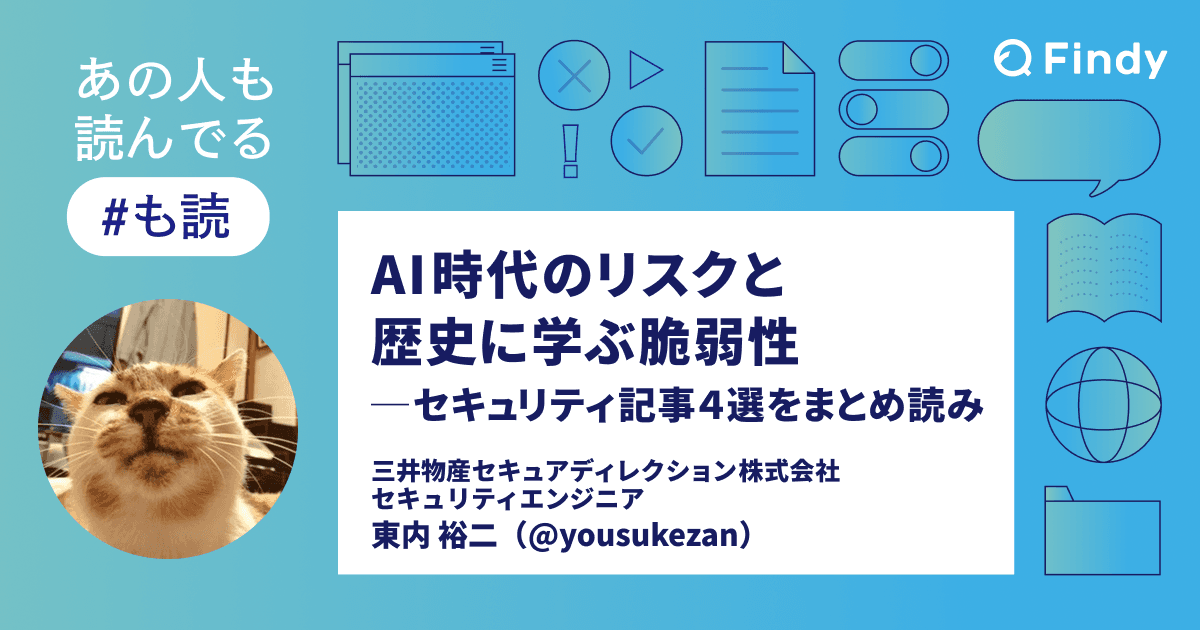「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
こんにちは。東内(@yousukezan)です。
相変わらず引きこもってAIとセキュリティの記事を中心に読んでいます。お盆が明けてもなかなか涼しくならなくてぐったりしています。
それでは、最近読んで良かったコンテンツの一部を紹介します。
【バイブコーディング】セキュリティについてまとめてみました【AI開発】
最近ではコードを書くときAIに任せきりになっていることが多いです。動かすだけならまあいいかとコードも読まず実行することも多く、変なコードが埋めこまれてたらひとたまりもないなあと思ったりもします。
この記事はそんな「バイブコーディング」と呼ばれるAIアシスタント主体の開発スタイルにおけるセキュリティと品質の課題を、筆者の経験を交えて人間とAIそれぞれの視点から整理した内容です。