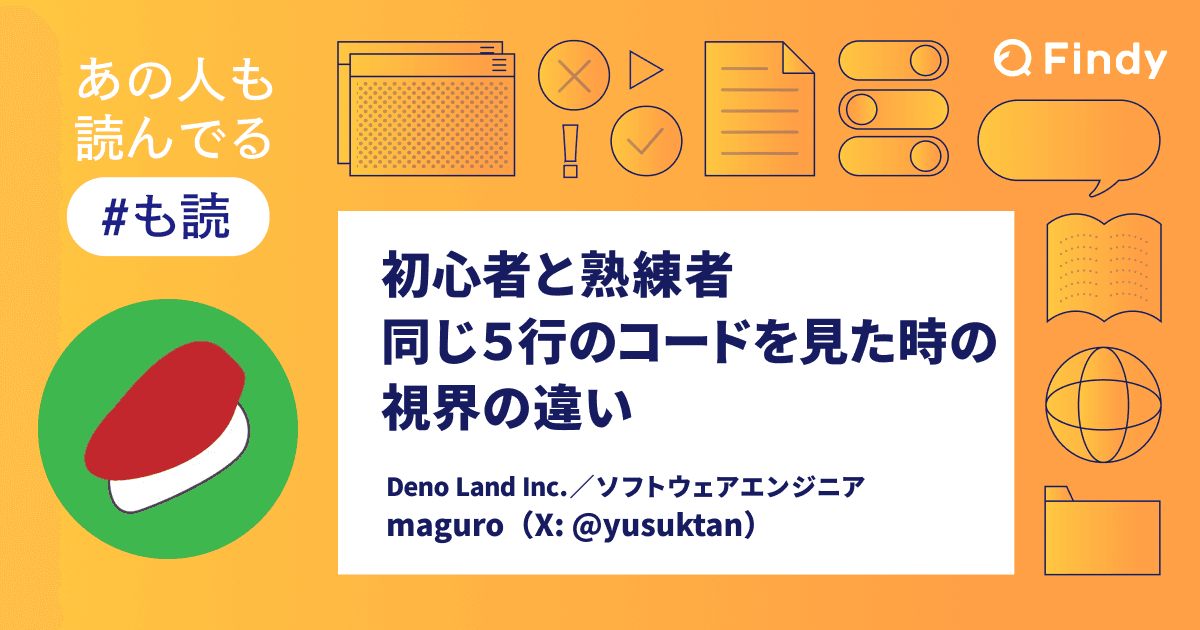「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
みなさんこんにちは。
「あの人も読んでる」、第12回目の投稿です。maguro(X @yusuktan)がお届けします。
初心者と熟練者、見ている世界の違い
2025年8月22日、素晴らしいエントリがZennにて公開されました。
瞬く間に拡散され、9月15日現在で1800強のいいねを集めるなど、猛烈な評価を得ているこのエントリ。僕はXのタイムラインに流れてきて読みはじめ、すぐに「これは珠玉の内容だ」と思いました。
これだけ拡散され、評価を得ているエントリですから、既に数多くの方が読んでいることと思いますが、本当に良い記事は宣伝しすぎるくらいでちょうどいいと思い、今回の「も読」で紹介することにしました。
詳しい内容はぜひ元の記事のほうを読んでいただければと思うのですが、ざっくり言うと以下のたった5行のJavaScriptコードを例に挙げて、これがエンジニアとしての経験値に応じてどのように見方が変わっていくのか、ということが述べられています。
async function getUserName(userId) {
const response = await fetch(`https://api.example.com/users/${userId}`);
const user = await response.json();
return user.name;
}
僕がこのエントリを素晴らしいと思った最大の理由は、シンプルな題材を使いながら、初心者と熟練者の見えている世界の違いを明解に表している点です。