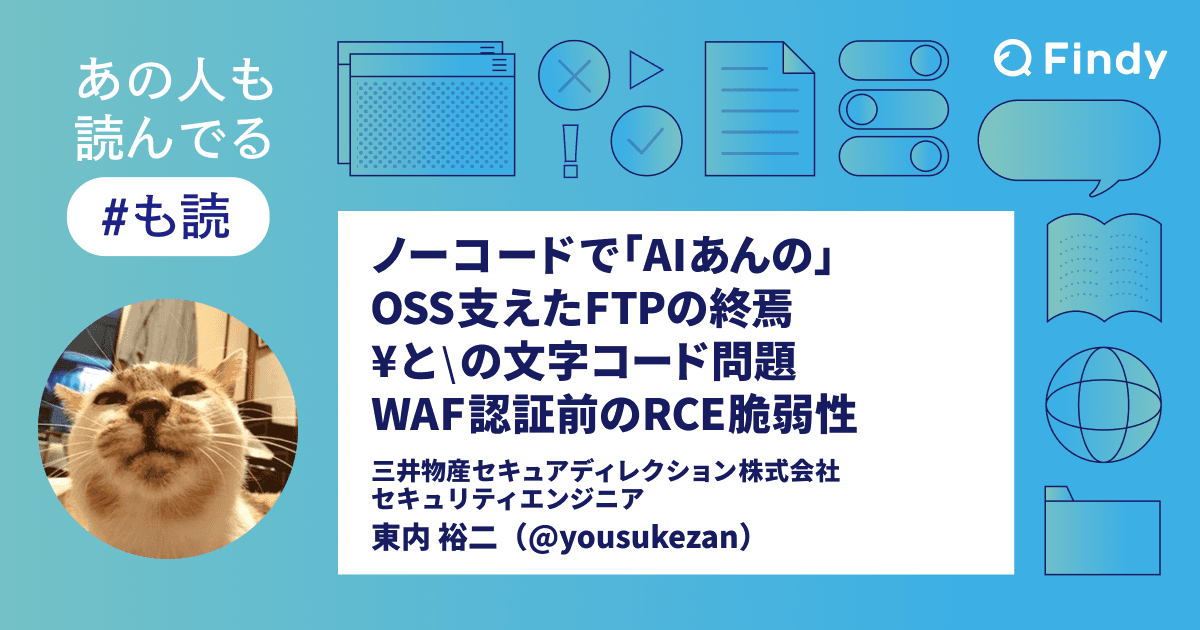「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
プログラミングなしで作る「AIあんの」(チャットボット版)
参議院選挙が行われ、新党「チームみらい」が議席を確保しました。YouTube LiveのAIチャットボット「AIあんの」が政策に関する質問にリアルタイムに答えていた点も印象的でした。
本記事では、このチャットボットの作り方を初心者向けに丁寧に解説しています。2025年の参議院選挙に向け、新党「チームみらい」のサポーターとして実際にAIあんのの開発に携わった著者が、その体験を基にノーコードツール「Dify」を使ったAIの構築手順を詳しく紹介しています。