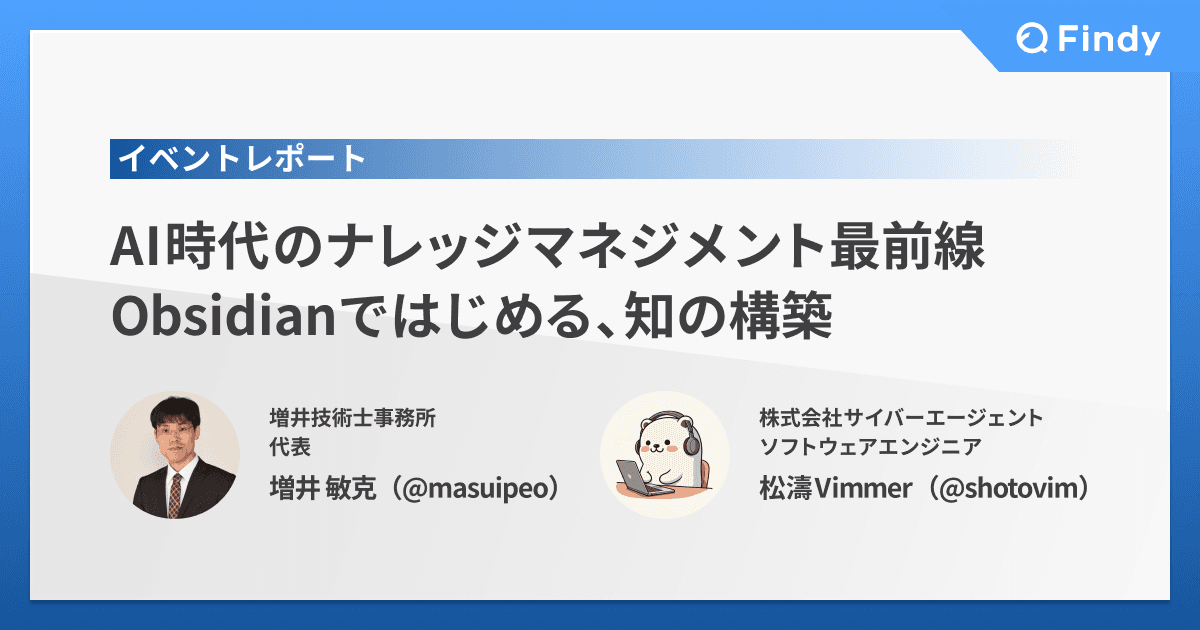本記事では、2025年6月26日に開催されたイベント「AI時代のナレッジマネジメント最前線 - Obsidianではじめる、知の構築 -」の内容をお届けします。イベントでは、増井 敏克 (@masuipeo)さん、松濤Vimmer (@shotovim)さんにObsidianを活用した「自分に合った知識管理の方法」「AI時代の知との向き合い方」をテーマに講演いただきました。当日はデモも含めてお話しいただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。
セッション① 増井 敏克氏
増井:今日はObsidianの基本的な使い方からAIとの連携についてお話します。
1年半ほど前に『Obsidianで“育てる”最強ノート術』も出版しており、今日はその内容にも触れながらお話しする予定です。
Obsidianとは
Obsidianはローカルで動作するノートアプリで、PKM(知識管理)アプリとも呼ばれます。
主な特徴はMarkdown形式でノートを作成することにより、ノート間を簡単にリンク出来る点や階層型タグ、豊富なプラグインによるカスタマイズが可能な点です。この点については、後ほど詳しく説明します。
Obsidianの使い方は人それぞれですが、最も一般的なのは知識管理でしょう。リンクとタグで知識を体系的につないでいくのが基本的な考え方です。それに加え、日記やライフログとして日々の記録や振り返りに使ったり、プロジェクトのタスク管理や進捗追跡に活用したりすることもできます。現にこのスライドもObsidianで作成しており、プレゼンテーションも可能です。
「自分用のWikipediaを作る」といった使われ方もしますが、覚えておきたいことを何でも書き留めておく、というのがObsidianの基本的なスタンスです。そして最近では、Markdownでローカルに保存されるこの仕組みを活かしたAI連携が話題になっています。
大事なのは「振り返り」
ノート作りで何より大事なのが「振り返り」だと私は思います。
Obsidianのノートは一度作って終わりではなく、デジタルの利点を活かして後から見返し、検索や要約を手軽に行うことができます。そのため、後でどう使うかを意識して記録することが大切ですが、ノートを書かないことには始まりません。Obsidianは手軽に書き始められるので、管理方法を考える前に思いついたことをどんどん書いていきましょう。
デジタルノートの大きな特徴は、書いた後も自由に書き換えられる点です。時間の経過と共に考え方が変わるのは自然なこと。これは自分だけのノートですから、他者を気にせず、どんどん内容を更新して「育てて」いってください。どう作り、何を書くかは人それぞれです。この「自分なりのノートを育てる」という意識が、私の本で「知を育てる」という言葉を使った理由でもあります。
では、どうノートを作るか。基本はフォルダではなく「リンク」で管理することです。Obsidianでは二重のかぎ括弧“ [[ ]]” でノート名を囲むだけで簡単にリンクでき、リンク先のノートには自動でバックリンクが表示されます。このようにノート同士を繋げられるため、1つのノートには1つのトピックだけを書き、できるだけ小さな単位で作っていくと、情報の再利用性が高まります。