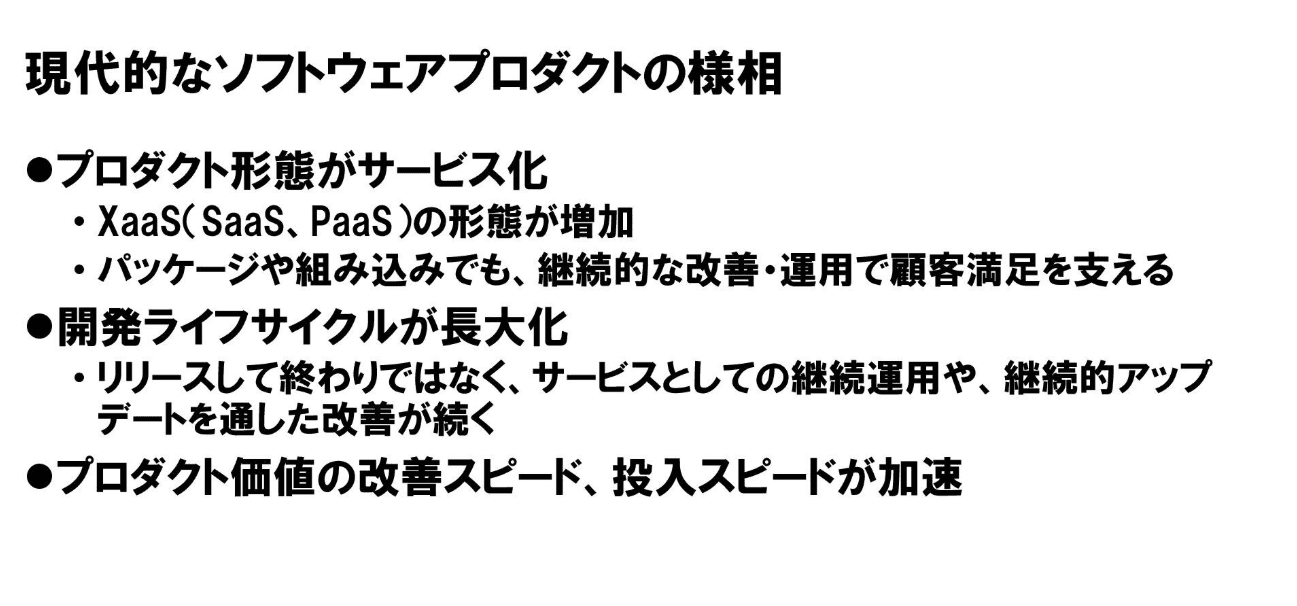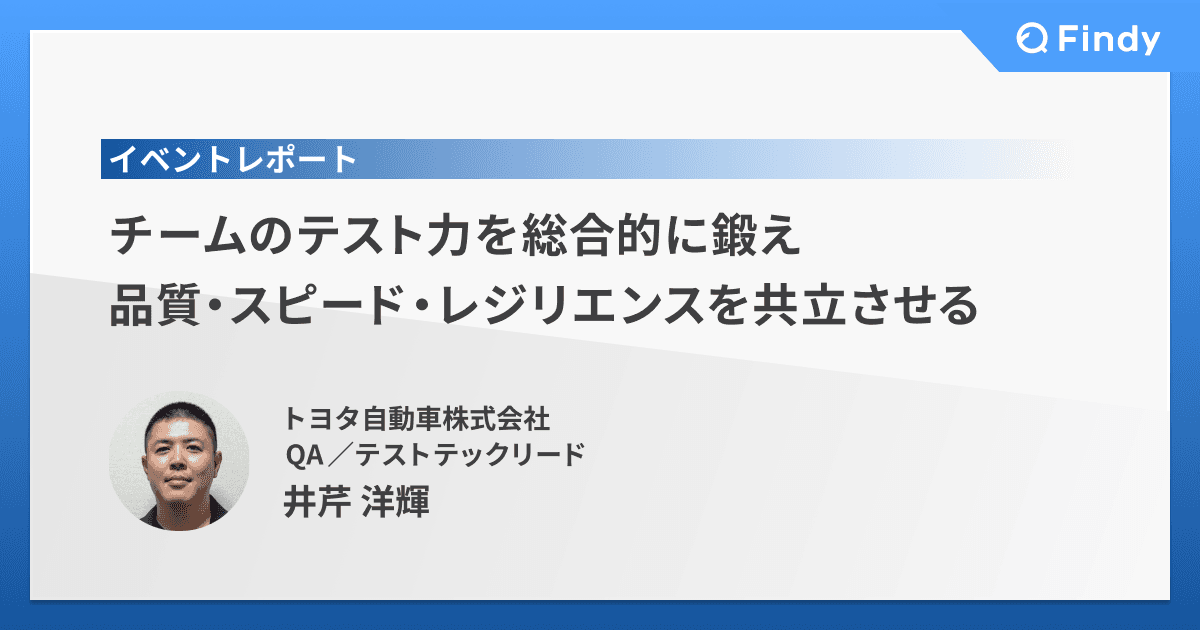本記事では、2025年7月8日に開催されたイベント「チームのテスト力を総合的に鍛えてソフトウェア開発の高品質と高スピードを両立させる実践技法」の内容をお届けします。イベントでは、『ソフトウェアテスト徹底指南書 〜開発の高品質と高スピードを両立させる実践アプローチ』の著者である、井芹 洋輝さんにご講演いただきました。イベント当日に回答しきれなかった質問についても、本記事にてご回答いただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。
井芹:本日は「チームのテスト力を総合的に鍛え、品質・スピード・レジリエンスを共立させる」と題し、お話しします。
私はこれまで開発者、テストエンジニア、コンサルタントとして様々なテスト業務に従事し、現在はトヨタ自動車でQA/テストのテックリードを務めています。社外ではJSTQB技術委員や、テスト設計コンテストU30クラスの初代審査委員長も担当しています。
継続的な開発に必要なのは、“品質、スピード、レジリエンスの共立”
なぜ今、品質・スピード・レジリエンスを共立させる必要があるのか。その背景となる、近年のソフトウェア開発を取り巻く状況変化からご説明します。
現在の大きな傾向として、SaaSやWebサービスに代表されるようにプロダクトの形態が「サービス化」しています。これはパッケージや組み込みの世界でも同様で、リリース後も継続的なアップデートで価値を提供することが一般的になりました。自動車業界でも、テスラのように高頻度なアップデートで顧客満足度を高める手法が広がっています。
このサービス化により、開発ライフサイクルも長大化しています。一度リリースして終わりではなく、継続的な改善によってプロダクトが長く成長し続けるためです。こうした環境での激しい競争を勝ち抜くため、開発のアプローチも変化しました。
従来は、案件ごとにプロジェクトチームを編成し、リリース後に解散する「プロジェクト型」が主流でしたが、継続的な改善が求められる現在では、同じチームがプロダクトを運用・改善し続ける「チーム型」へ移行しています。それに伴い、優秀な人材を都度集めるのではなく、チーム自身の開発力を継続的に高め、プロダクト価値を支え続けることが重視されるようになっているのです。