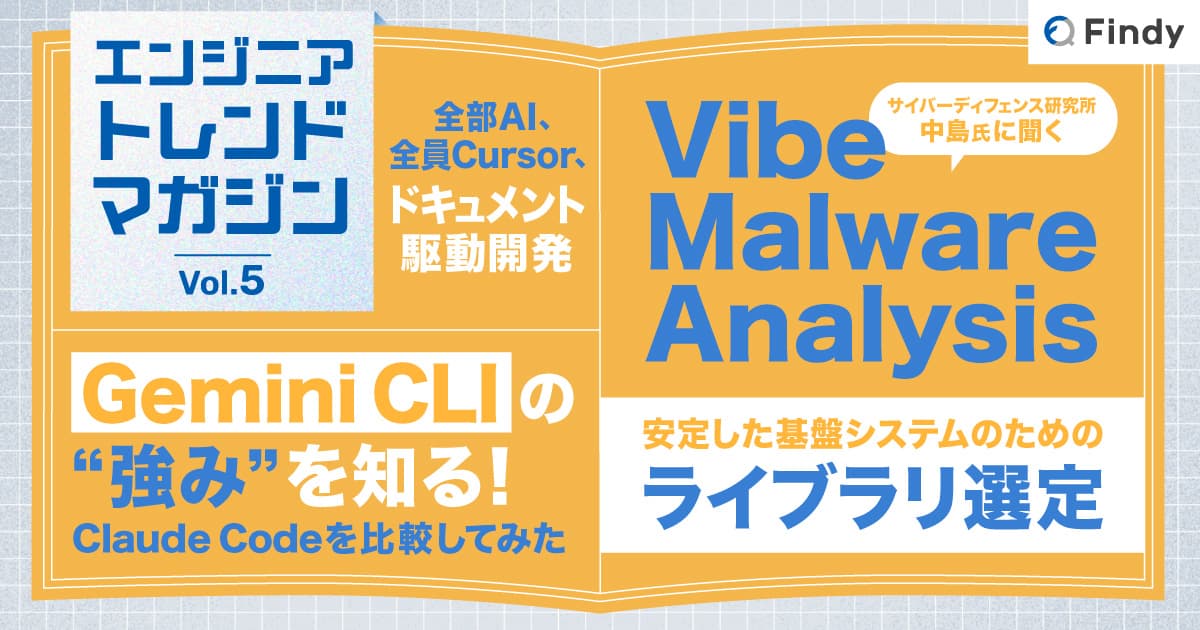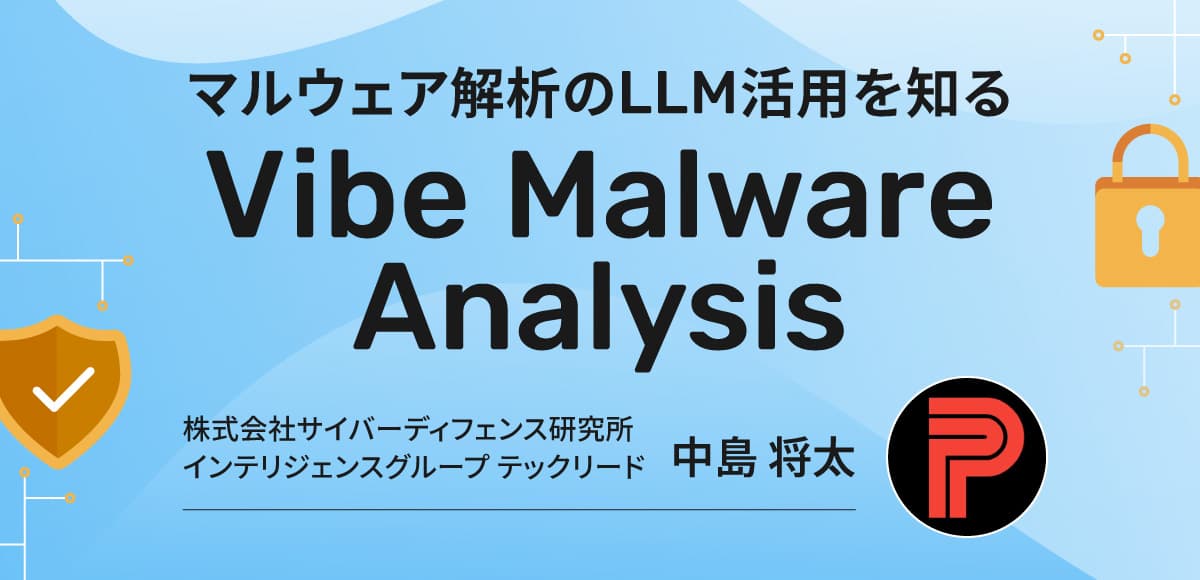「エンジニアトレンドマガジン」は、Findyの開催イベントから、エンジニアの知見と技術トレンドを編集部がピックアップしてお届けする特集記事です。今月は、マルウェア解析におけるLLM活用の現在地、TypeScriptを用いた基盤システム構築、Gemini CLIとClaude Codeの性能比較、LLMによる開発民主化の取り組みを特集。イベントご参加者の声やアーカイブ動画もご覧いただけます。
【目次】
- マルウェア解析のLLM活用を知る──Vibe Malware Analysis
- Gemini CLIの“強み”を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた
- 安定した基盤システムのためのライブラリ選定
- 全部AI、全員Cursor、ドキュメント駆動開発 〜DevinやGeminiも添えて〜