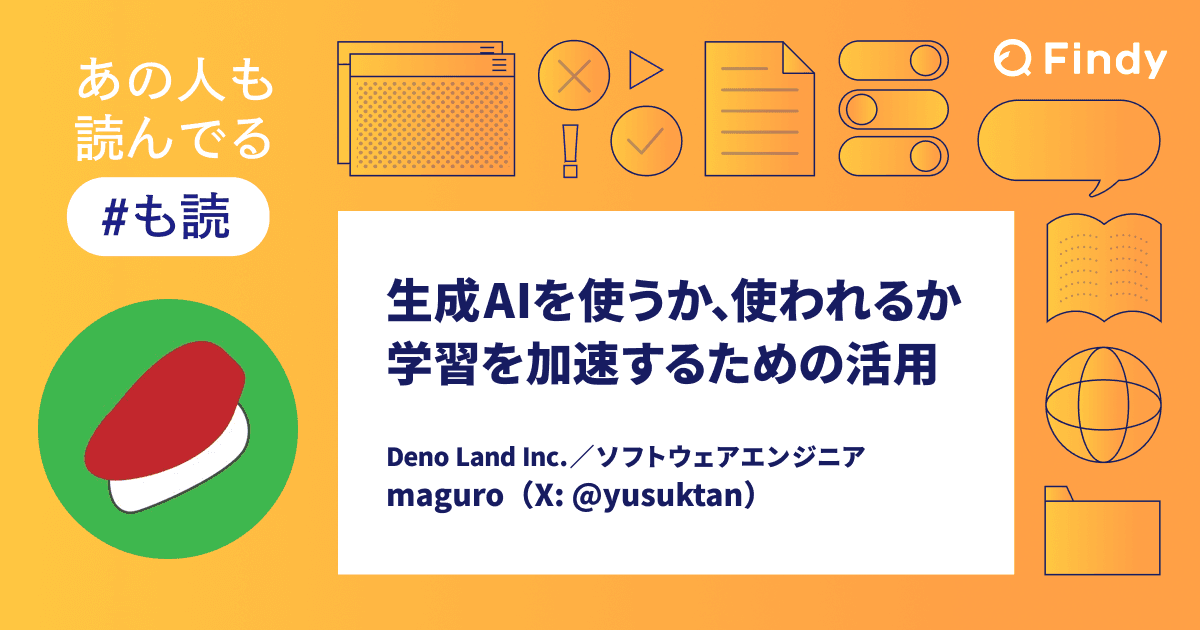「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
みなさんこんにちは。
「あの人も読んでる」、第4回目の投稿です。maguro (X @yusuktan)がお届けします。
今回のテーマ: 生成AIを使うか、使われるか - 学習を加速するための活用
生成AIの急速な発展が目覚ましい昨今ですが、少なくとも現時点では、使う側の技量次第で毒にも薬にもなるといった状況です。
特に初学者にとっては、生成AIをうまく活用して質・量ともに高い学習を加速させることもできれば、分からないところを分からないまま表面的に受け取ってしまい、かえって学習の阻害になるリスクもあるでしょう。
このテーマに関連して、以下の記事をご紹介します。