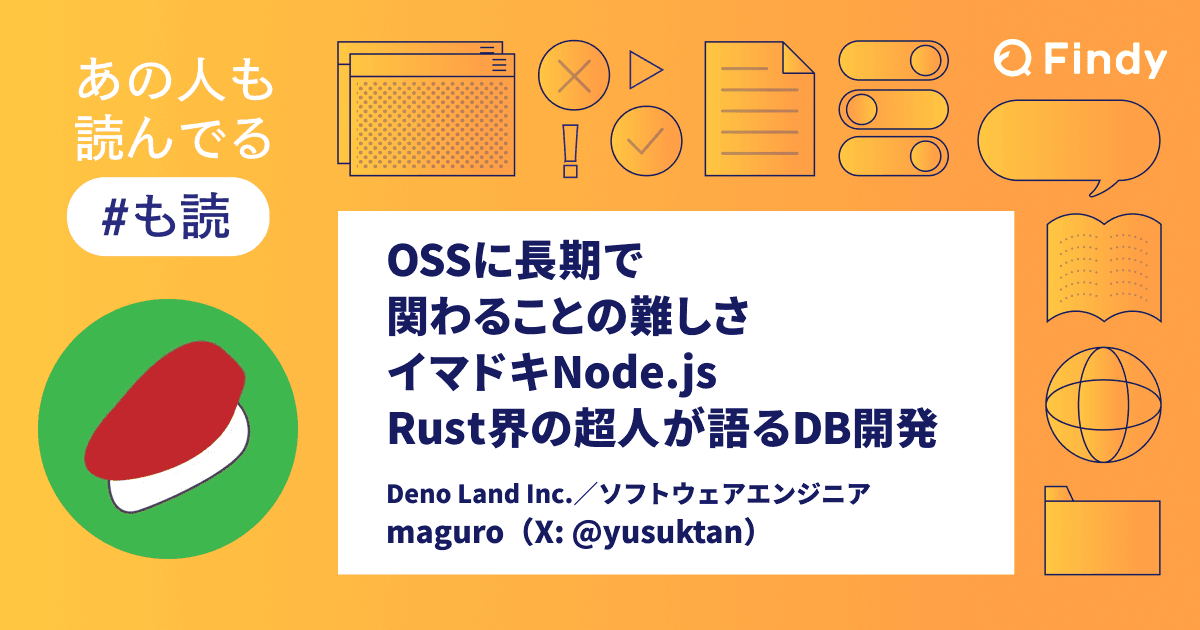「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
みなさんこんにちは。
「あの人も読んでる」、第9回目の投稿です。maguro (X @yusuktan)がお届けします。
今回は雑多に
いつもは何かしらのテーマに沿ってコンテンツを紹介していることが多いのですが、今回は特にテーマを決めずに、最近気になった情報を雑多にお届けしようと思います。
1つのOSSに継続的に貢献する
最初に紹介するのは、Findyメディアに掲載されている あなたの知らないOSSの裏側 - tokio-rsで気付いたOSS運営の"リアル"3選 です。Rustの非同期ランタイムであるTokioプロジェクトのメンテナとして活動されているmox692さんによる寄稿です。
TokioはRustエコシステムにおいてかなり重要な立場にあるクレート(ライブラリ)です。非同期プログラミングを行う際はほぼ間違いなくお世話になります。このような重要なプロジェクトがどのようにメンテナンスされているのかを知ることのできる興味深い記事でした。