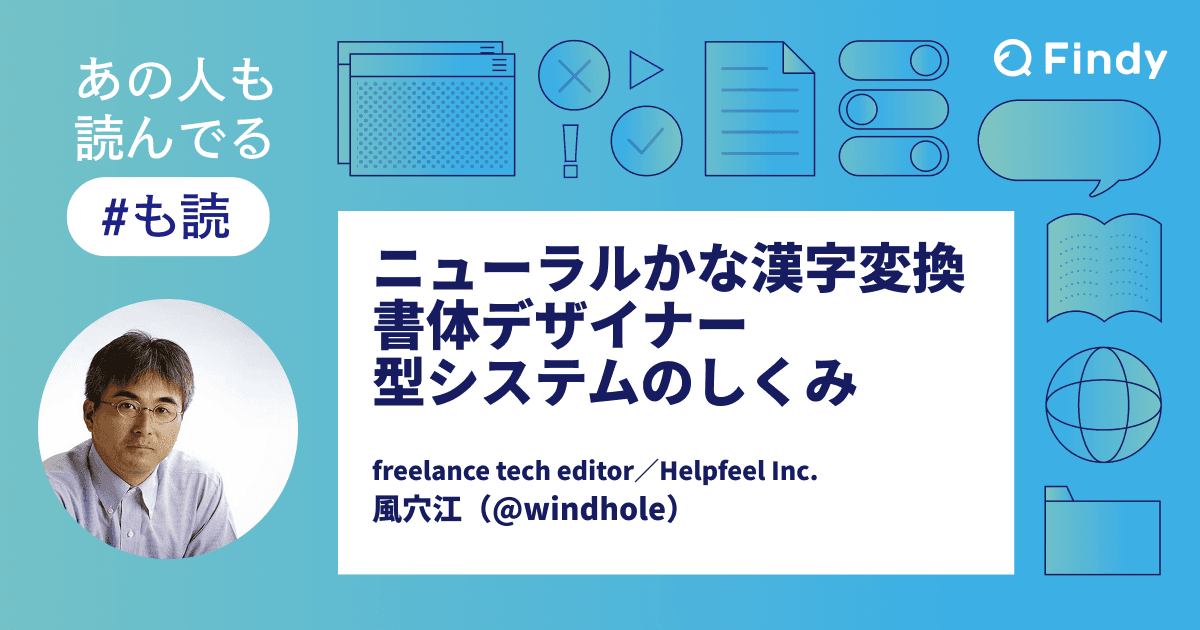「あの人も読んでる」略して「も読」。さまざまな寄稿者が最近気になった情報や話題をシェアする企画です。他のテックな人たちがどんな情報を追っているのか、ちょっと覗いてみませんか?
こんにちは。風穴(かざあな)です。
所用があって実家(青森県)に来ているのですが、この辺は、今&これからが桜の見頃です。二度目のお花見でちょっと得した気分。ちなみに、実家の庭では梅の花も咲き始めました。
それでは、最近読んで良かったコンテンツ(の一部)を紹介します。
ニューラルかな漢字変換システム
ニューラル言語モデルを採用したかな漢字変換エンジン「Zenzai」と、それを組み込んだ日本語入力システム「azooKey on macOS」の開発記。2024年度の未踏に採択された開発プロジェクトです。新しいかな漢字変換エンジンを作るために何をしたかが簡潔にまとまっていて、読みやすく面白い記事でした。