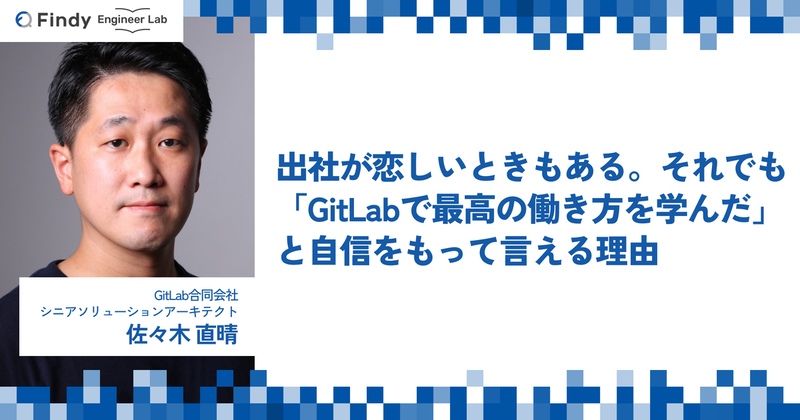
昨今、RTO(Return to Office)の流れに代表されるように、最適なワークスタイルについての議論が活発になっています。しかし、この議論の本質は、働く「場所」の選択にあるわけではありません。フルリモート、ハイブリッド、フル出社——どれを選択するにせよ、最大の成果を出すための組織づくりの重要性が問われているのです。
2023年9月、『GitLabに学ぶ 世界最先端のリモート組織のつくりかた ドキュメントの活用でオフィスなしでも最大の成果を出すグローバル企業のしくみ』という書籍が発売されました。この書籍では、創業当初からフルリモートを貫くGitLab社のコラボレーション設計に関する深い哲学を知ることができます。
そこでFindy編集部では、書籍の監修を務めたGitLab シニアソリューションアーキテクトの佐々木 直晴さんに取材を実施。これからの働き方を考えるすべての企業にとって参考になるであろう、GitLabの実践から学べる組織づくりのヒントについてお話を伺いました。
GitLabのエンジニアが考えるリモートワークの本質とは
――佐々木さんのこれまでのキャリアについて簡単に教えてください。
私は2010年に新卒で野村総合研究所というSIerに入社し、システムエンジニアとしてキャリアをスタートしました。約11年の在籍期間中、大規模なシステム開発やITインフラの技術課題解決などに携わっていました。
その後、知人のリファラルでGitLabから声をかけていただき、プリセールスエンジニアとして参画することになりました。
――GitLabは世界最先端のリモート組織を有するグローバル企業です。国内企業から転職して、最初に感じたことは何ですか?
前職での最後の2年間は、新型コロナウイルスの影響でリモートワークをせざるを得ない状況。必要に迫られてリモートワークを頑張ってやっていました。
一方、GitLabのリモートワークは「リモートワークを前提とした企業のリモートワーク」です。この違いは非常に大きく、価値観が根本的に異なると感じました。
――佐々木さんが2022年のデブサミで発表された「GitLabで学んだ最高の働き方」を拝見すると、リモートワークはただ単に「在宅勤務」を指しているのではなさそうだと感じました。
はい。単に在宅で仕事をするという概念より、もっと広いものだと理解しています。一言でいえば、「自分以外の他者とコラボレーションすること」そのものがリモートワークと同義だと考えています。
現代の仕事は自分だけで完結することはほとんどなく、他者との認識合わせや依頼・回答など、さまざまなコラボレーションが必要です。自分のコンテキストと他人のコンテキストをうまく共有しながらコラボレーションしていくこと、これが私たちの考えるリモートワークの本質です。物理的な所在地はあくまで要素の一つで、本質ではありません。
――GitLabのリモートワークの考え方は、企業理念とも関係していますか?
GitLabの企業理念「Everyone can contribute」は、どこにいてもすべての人が貢献できるという考え方。地方在住の優秀なエンジニアにとっては、リモート環境だからこそプロダクト開発に貢献できるわけです。場所を問わない働き方を前提にしたコラボレーション設計こそが、私たちのリモートワークの核心なのです。
▼The GitLab Handbook|GitLab Mission|Everyone can contribute with GitLab
フルリモートだから感じる「オフィス出社のうらやましいところ」
――オフィス出社もフルリモート勤務も経験している佐々木さんが思う「対面コミュニケーションの良さ」について教えてください。
対面コミュニケーションの良さは、同じ物理的な空間に身を置いて、身体的な経験を共有できることだと思います。リモートでもZoomで話はできますが、「ちょっと気分転換に外のカフェに行きませんか?」と誘うことは難しい。カフェに向かう道中でも、「外に出ると目が痒くて仕方ないよ」「花粉症なんですね」「今週末はまた冷え込むらしいよ」といった会話が自然と生まれます。物理的に同じ空間にいることで、本来の目的以外の情報交換という副産物が生まれるんですよね。
――そういった副産物が仕事にも良い影響を与えることはありますか?
多々あります。目的外で得た情報が思いがけずつながることがよくあるんです。たとえば、「あの人は最近これに困っていた」という情報と、別の人から聞いた「こういう発見をした」という情報が、自分の中で偶発的につながって化学反応を起こす。いわゆるセレンディピティですね。そうした副産物が多ければ多いほど、どこかでスパークする可能性が高まります。
――オフィス出社を恋しく感じることはありますか?
それはありますね(笑)。たとえば、誰かの出張土産が置いてあるコーヒーサーバー周りでの立ち話。会話を通じて新しいつながりができる瞬間は懐かしいです。でも一番は昼食。オフィスだと「そろそろ行きますか」と誘い合って、みんなでワーッと行くじゃないですか。あの感じが恋しいです。
――仕事の進め方やチームワークの観点で、対面の方が良いと感じる事例を教えてください。
特にソフトウェア開発の領域では、図で説明したいシーンがよくあります。ネットワーク構成やシーケンス図など、言語で議論する前に視覚的な情報で共有したほうが効率的なケースは多いです。
リモートでも使えるホワイトボードツールもありますが、物理的なホワイトボードには勝てません。ホワイトボードの前では、人対人で話すのではなく、同じ方向を向いてホワイトボードに対して話すという形になりますよね。「これはこうじゃない?」と指さしながら、全員が同じ方向を向いて問題と向き合う感覚は、オンラインのホワイトボードツールでは得られない体験ではないでしょうか。
――では、GitLabではリモートワークの課題をどのように解決しているのでしょう。
情報共有における工夫はしていますね。GitLabでは文字に残すことを重要だと考えているため、Zoomで話し合った内容も必ず記録します。
特徴的なのはSlackの扱いです。具体的には、ログを90日で自動的に消す設定にしています。その理由は、重要な情報はより整理された形でドキュメント化すべきだからです。「今日のMTGは何時からですか?」といった一時的なやりとりはSlackで十分ですが、製品のバグなどの重要な情報は大元のドキュメントに反映すべきです。真の情報を一元管理することで、同じ情報が複数箇所で議論される無駄を省けますから。
――他にはどのような課題がありますか?
新入社員のオンボーディングは、隣の席に詳しい人がいるオフィスワークの方が有利な面もあります。フルリモートの会社に入社するとなるとなおさら不安ですよね。私の場合、GitLabへの入社の前日になっても何をするのか決まっておらず、本当に大丈夫なのかとマネージャーに確認したほどです(笑)。
だからこそGitLabでは、そこを特に意識して工夫しています。オンボーディングイシューで詳細なタスクリストを提供し、オンボードバディ制度で一人ひとりにサポート担当がつくんです。マネージャーからは「入社したらびっくりするぐらい万全の体制が整っているから安心してきてください」と言われていましたが、実際、予想をはるかに上回るオンボーディング体験ができました。
――チーム内のコミュニケーションや情報共有をスムーズにするための工夫はありますか?
定期的に会うことも大切だと考えています。会社全体では年に1回、世界中のメンバーが一箇所に集まる機会があります。また地域ごとのチーム、たとえば東京のメンバーであれば、週1回希望するメンバーが集まれる場所が確保されています。そこに行くとさまざまな部署の人と話せるんです。毎日一緒にランチに行くことはできなくても、時々は実際に会って交流する体験を大切にしています
仕事の効率を上げる同期・非同期コミュニケーションのコツ
――GitLabでは、非同期コミュニケーションをどのように位置づけていますか?
非同期コミュニケーションとは、相手がそこにいることを前提としないやり取りです。私の感覚では、相手すらいなくてもいいものです。誰がいつ見るかわからなくても、ドキュメントに情報を残すことで時空を超えた情報共有ができます。
同期と非同期のコミュニケーションの使い分けは、不確実性の高さで判断することが多いです。たとえば、相手の反応によって次の対応が変わるようなケース。次の対応をすべて想定した非同期コミュニケーションはコストが高すぎますよね。「これについてどう思いますか?」「こう思います」「ではこうしましょう」といった流れは、同期コミュニケーションの方が効率的です。
このように、不確実性が高い領域やお互いの認識合わせが必要な場面では同期コミュニケーションを選びます。ある程度選択肢が絞られて、不確実性が低くなった段階で非同期に切り替えるのがポイントです。
――デリケートなコミュニケーションや感情的なニュアンスが重要な場面もありますよね。その場合はどうしていますか?
そういう場面でも、できるだけ非同期でやるよう意識しています。もちろん本当にリスクが高い場合はZoomなどを使いますが、そうでなければ、誤解がないよう意図を明確に書くことを心がけています。
GitLabのバリューには「Assume Positive Intent(相手の意図を前向きに捉える)」という考え方があり、これがとても重要です。相手の言葉に悪意を読み取らず、前向きな意図を想定するという文化が根付いています。
▼The GitLab Handbook|GitLab Values|Assume positive intent
――発信側も受信側もお互いに心がけるというのは、リモート前提のGitLabならではの素晴らしいバリューですね。そのほか、非同期コミュニケーションで大事なことはありますか?
非同期コミュニケーションを効果的に行うには、情報を後から見つけやすいよう整理しておくことが重要です。そこで私たちは「Single Source of Truth(SSOT)」という考え方を取り入れています。これは、すべての情報を1か所にドキュメント化してまとめる概念です。
英単語の辞書を思い浮かべてみてください。どの単語がどこに載っているか誰でもわかり、誰でもアクセスできる一つの情報源になっています。これを会社のルールや知識にも適用できれば、コミュニケーションの量が大幅に減らせるという考え方です。
たとえば、「お客様先に行くまでに食べた弁当代はどう経費精算すればいいのか」という疑問があったとします。これがSSOTとして整理されていれば、「このページのこの項目に書いてある」と辞書を引くような感覚でアクセスできる。簡単に情報を探せるという状態を作ることができれば、他の人に確認したり、質問の返事を長時間待ったりする必要がなくなります。
▼The GitLab Handbook|GitLab Values|Single Source of Truth
――先ほどSlackのログを90日で消す話がありましたが、それもこのSSOTの考え方に関連しているのですね。
はい、まさにそうです。Slackは口頭と文書の中間的な性質を持ち、気軽なコミュニケーションに適していますが、重要な情報の最終的な置き場所としては適していません。重要事項をきちんと構造化されたドキュメントに反映することで、Slackの複数チャンネルで同じ情報が議論されることを防ぐ。これによって無駄なコミュニケーションを減らせます。
こういった情報管理の考え方は、リモートワークだけではなくオフィスワークでも同様に価値があるものです。どのような働き方であっても、情報を一元管理し、必要なときに適切にアクセスできる環境を整えることは、組織の生産性と透明性を高める基本だと考えています。
▼非同期コミュニケーションを機能させるには何が必要か?オールリモートのGitLabの働き方に見る “ルールと文化”のつくり方
働き方が変わるとプロダクトも人生も変わる
――フルリモート環境かつグローバル企業であることは、どのようにGitLabの強みとなっていると感じますか?
GitLabは会社運営そのものを「GitLab」を使って行っています。ドキュメントは「GitLab」に残し、マージリクエストという機能を使って社内の情報を積み上げていくんです。
私たちは自分たちのプラットフォームを世界中でドッグフーディングしながら開発・改善しています。自分たちがフルリモートで働いているからこそ、リモートワークに最適な機能が実装されていきます。これはGitLabならではの強みではないでしょうか。
製品の細部にはGitLabの企業文化が宿っています。もしも「東京なら東京オフィス、西海岸なら西海岸オフィスに必ず出社する」という世界線だったとして、今と同じ製品はできていないでしょうね。「Everyone can contribute(誰もが貢献できる)」というミッションを支えるリモート体制があるからこそ、世界中から優秀な人材を採用でき、その多様な知見が製品に反映されていると考えています。
――実際にリモートワークで生産性は向上するのか、気になるところです。
同じメンバーでオフィスで働いたことがないため、比較できないんです(笑)。もしかしたら、オフィスに集まれば今より生産性が上がるかもしれません。
ただ個人的には、リモートワークで生産性は上がっていると感じています。好きな時間に髪を切りに行けたり、気分転換に席を離れても誰も文句を言わなかったり。私自身は夜型で、子どもが寝静まった時間に集中して作業するのが好きなので。
――GitLabでの働き方を通じて、プライベートにはどのような影響があったのでしょうか。
QOLは確実に上がっています。まず家族と過ごす時間が増えました。これは他のどんなものにも代えられない価値があります。以前の会社では、忙しい時期は子どもが起きる前に家を出て、帰宅したときには子どもが寝ているということがありました。子どもは平日の父親を知らない状態だったんですよね。
今の働き方は、私にとって完全にノックアウトファクター、つまり決定的な要素となっているんです。この働き方ができなければ厳しいと感じるほど、取り替えがきかない価値があります。
人生における優先順位の感覚も変わったように思います。「ライフワークバランス」という言葉がありますが、今ではこの表現に違和感を覚えるんです。あれはライフとワークの二者択一のように感じられますが、実際はワークもライフに含まれるべきもの。どちらを取るかという問題ではなく、ライフの中にワークをどう位置づけるかが本質だと思うようになりました。
「どう働くか」は「どう生きるか」に含まれる問題。GitLabの働き方は、その両方を総合的に考えられる環境を提供してくれています。
――これまでのお話を踏まえ、最適な働き方を模索する企業へのアドバイスをお願いします。
働き方の変革に取り組む際、まず重要なのは「なぜそれをするのか」という目的の共有です。ドキュメント作成の習慣やツールの導入といった実践面だけを先行させるのではなく、それによって得られる具体的なメリットを全員で合意することから始めるべきです。
働き方の最適解は、組織の目的や文化によって異なります。正解はひとつではないので、各組織がそれぞれの強みを活かせる設計をすることが大切です。GitLabでは世界中の優秀な人材を採用するという目的からフルリモートを選択しましたが、他の組織では違う選択が最適かもしれません。重要なのは形態ではなく、効果的なコラボレーションが可能かどうかだと思います。
取材・文:河原崎 亜矢
編集:Findy Enginee Lab編集部
 シェア
シェア はてブ
はてブ